| HOME>研究書 | ||
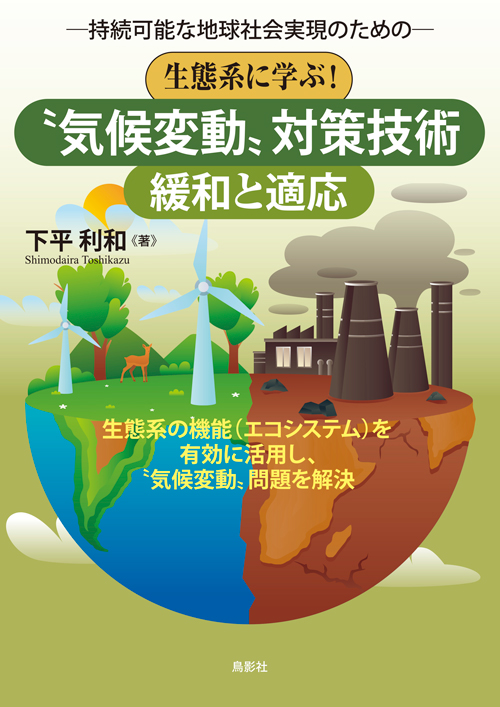 |
持続可能な地球社会実現のための生態系に学ぶ!〝気候変動〟対策技術【緩和と適応】
下平利和
生態系の機能(エコシステム)を有効に活用し、〝気候変動〟問題を解決 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2200円(税込) |
下平 利和(しもだいら としかず) 1951年長野県岡谷市生まれ。 1978年環境計量士取得(登録)以来、環境分析・測定・調査・評価・対策、及び水処理、廃棄物処理の業務に従事。 現在、NPO環境技術サポートJAPAN代表、自然エネルギー信州ネットSUWA会員、諏訪湖創生ビジョン推進会議構成員。 著書 『生態系に学ぶ 次世代環境技術』(2007) 『生態系に学ぶ! 廃棄物処理技術』(2011) 『生態系に学ぶ! 湖沼の浄化対策と技術』(2016) 『生態系に学ぶ! 地球温暖化対策技術』(2019) 『生態系に学ぶ! “気候変動”適応策と技術』以上、ほおずき書籍(2020) 著者の主な気候変動対策関連技術(著書「生態系に学ぶ! 地球温暖化対策技術」に概要を掲載) 【研究開発】バイオマス系廃棄物の堆肥化、固体燃料化、減量化、飼料化、バイオガス化技術、「循環空気調和型堆肥化(発酵)施設」の開発(特開2000-044372)。 【技術提案】─バイオマス利活用の加速的推進に向けて─「高温好気発酵法によるバイオマス系廃棄物の減量化・固体燃料化・堆肥化」(長野県「「水循環・資源循環のみち2010」構想」、「生活排水汚泥(バイオマス)利活用にかかる技術提案」) 【政策提言】脱原発・低炭素化社会の実現に向けた「地域分散型再生可能エネルギーシステムの構築」(「1市町村1自然エネルギー」の自助・共助・公助:スマートグリッド日本版) eco japan cup「グリーン・ニューディール準優秀提言」(2012) |
|
発刊日 |
||
2025年11月4日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-182-4
|
||
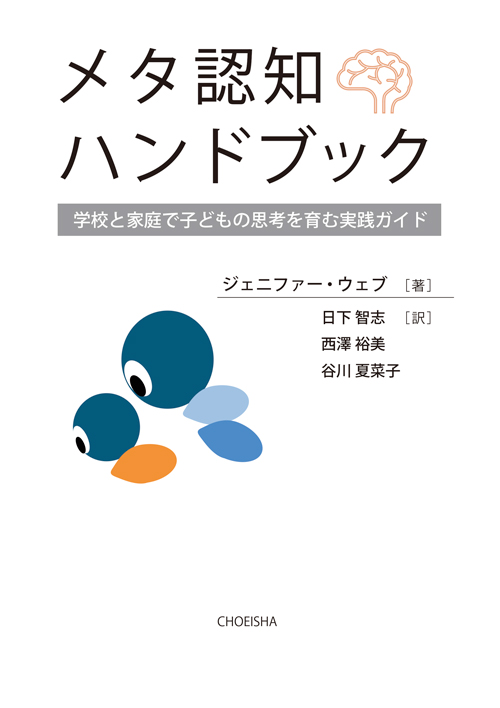 |
メタ認知ハンドブック 学校と家庭で子どもの思考を育む実践ガイド ジェニファー・ウェブ 著
人間の脳が持つ驚異の学習能力を伸ばそう! |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
ジェニファー・ウェブ Jennifer Webbは、ウェイクフィールドの学校で教頭兼教務主任を務めています。彼女は、リーズの活気ある芸術の中心地チャペルタウンで育つという幸運に恵まれ、イギリスとカリブの二重の文化的背景、そして力強い女性たちに囲まれた家庭の中で影響を受けてきました。 低所得のひとり親家庭に育ちながらも、オックスフォード大学マートン・カレッジで英文学を学ぶ機会を得て、その後はウェスト・ヨークシャーのさまざまな学校で教鞭をとってきました。 彼女は多くの読者を持つブログ「FunkyPedagogy.com」を運営し、「The Reading List Project」の創設者でもあります。また、教師や英語科向けに人気の高い継続的専門能力開発(CPD)プログラムを展開しています。 素晴らしい夫と2人の息子と過ごす時間を大切にしながら、読書にも情熱を注いでいます。 著書には、文化的貧困を乗り越えるための英文学の教え方を探る『How to Teach English Literature: Overcoming Cultural Poverty』や、『Teach Like a Writer』があり、いずれもJohn Catt社から出版されています。 |
|
発刊日 |
||
2025年8月27日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-151-0
|
||
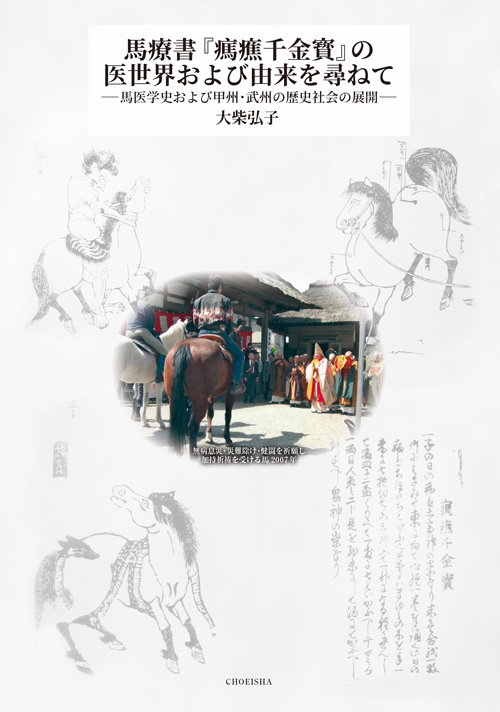 |
馬療書『㾺癄千金寳』の医世界および由来を尋ねて —馬医学史および甲州・武州の歴史社会の展開— 大柴弘子
「バショウ」とも呼ばれ昭和20年代まで活用されていた病馬の治療書『㾺癄千金寳』 |
|
価格 |
著者略歴 | |
4180円(税込) |
大柴弘子(おおしば・ひろこ) 1941年 東京に生まれる。1944~1959年 山梨県北杜市高根町清里村(旧樫山村)在住。 1962年 中央鉄道病院看護婦養成所卒(看護師)1966年 埼玉県立女子公衆衛生専門学院卒(保健師) 1977年 武蔵大学人文学部社会学科卒 1994年・2002年 東京都立大学大学院修士課程卒・同大学院博士課程単位取得退学(社会人類学専攻) 職歴:国鉄大宮鉄道病院、厚生連佐久総合病院健康管理部および日本農村医学研究所、南相木村、信州大学医療技術短期大学部看護学科、各勤務。昭和大学保健医療学部、厚生省看護研修研究センター等非常勤講師。現在、湖南治療文化研究所主幹 著書:(郷土誌・民俗調査関係、以下鳥影社) 『甲州樫山村の歴史と民俗I』(2010) 『甲州樫山村の歴史と民俗II』(2017) 『18世紀以降近江農村における死亡動向および暮らし・病気・対処法』(2015) 『近世の樫山村・浅川村および村成立過程 序』(2020) |
|
発刊日 |
||
2025年4月12日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-141-1
|
||
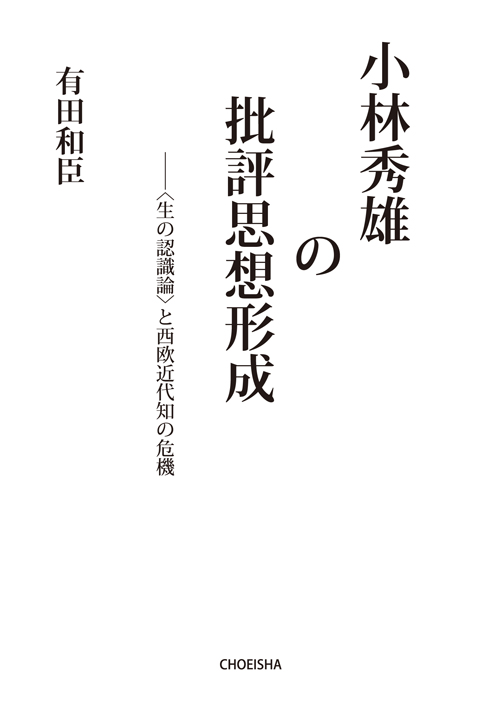 |
小林秀雄の批評思想形成 —〈生の認識論〉と 西欧近代知の危機
有田和臣 小林秀雄の批評文はニーチェ、西田幾多郎ら「生の哲学」系著作群からの〝借用〟に満ちており、それらが西欧近代知の危機乗り越えの道筋を示す意図のもとにあった事実を解明する。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
6820円(税込) |
有田和臣(ありた かずおみ) 1962年生まれ。早稲田大学第一文学部卒、立教大学大学院博士前期課程修了、筑波大学大学院博士後期課程単位取得満期退学、現在佛教大学文学部教授。主要論文:「〈女性の身体〉を奪還する少女―山田詠美「風葬の教室」と一九八〇年代のフェミニズム動向」(『京都語文』2019年11月)、「『「ごん狐』における物語の〝起点〟と〝源泉〟―猟師生活と兵十・茂助(茂平)の位相」(『京都語文』2016年12月)、「『春琴抄』と『小説の筋』論争―〈鳥〉に喩された芸術論小説」(『京都語文』2013年11月)、「『千と千尋の神隠し』論―『千の顔をもつ英雄』とニュータウンの幻影」(『京都語文』2011年11月)、「『伊豆の踊子』における〈裸体への視線〉―エキゾチック空間を生きる『私』と栄吉」(『京都語文』2010年11月)、「川端康成「古都」と〈トポス〉としての京都―千重子〝再生〟の主題と「四神相応」への夢」(『佛教大学総合研究所紀要別冊』2008年12月)、「眼の陶冶と帝国主義(四)―大正期文芸教育論と生命主義芸術教育論」(『京都語文』2003年11月)、「〈眼の陶冶〉と帝国主義(三)―大正期芸術教育論に見る国民国家形成の影」(『文学部論集』佛教大学文学部、2003年3月)、「〈眼の陶冶〉と帝国主義(二)―大正期文芸教育論の源流」(『京都語文』2002年10月)、「〈眼の陶冶〉と帝国主義(一)―大正期文芸教育運動の芸術愛好」(『京都語文』2000年10月)、「一葉『たけくらべ』における『水』の意味―水辺の遊興空間と文明開化」(『京都語文』1999年10月)、「三島由紀夫と『卵』―戦後から経済成長へ」(『京都語文』1998年10月)、「マンガを使った『読み方』の技術」(『教育技術』明治図書、1997年10月)、「初期小林秀雄の思想形成―ニーチェ『力への意志』と『宿命』」(『稿本近代文学』1994年11月)など。 |
|
発刊日 |
||
2025年3月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-149-7
|
||
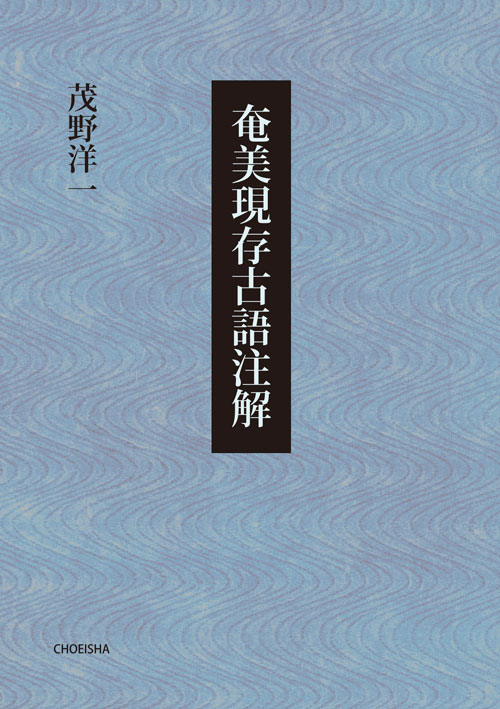 |
奄美現存古語注解
茂野洋一
消えゆく言葉に残された「いにしへのいぶき」 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
茂野 洋一(しげの よういち) 1939年 東京に生まれるも、1943年に鹿児島に疎開、空襲で全てを失い父は鹿児島居住を決めた。 1963年 鹿児島大学文理学部卒・鹿児島県立高校教諭 1994年 南日本新聞社主催の懸賞小説の『新春文芸小説部門』で「紙の卒塔婆」が受賞 2000年 定年退職を機に奄美・沖縄の歴史民俗研究のために上京 2001年 「道之島遠島記」が第二回『中・近世文学大賞』創作部門優秀賞を受賞 「道之島遠島記」を出版 2005年 歴史小説「南島古潭」出版 2007年 「奄美現存古語註解」をオンデマンド方式で出版 2024年 歴史小説「重野安繹伝」出版 |
|
発刊日 |
||
2024年12月7日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-118-3
|
||
 |
環境教育学 —気候変動〜食の安全・安心—
今井清一/今井良一
本書は『増補改訂版 環境教育論 現代社会と生活環境』を基本に、気候変動や食品表示法など、現状に合わせ多くの章で加筆・修正している。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2750円(税込) |
今井 清一(いまい せいいち) 1938年 神戸市に生まれる。 神戸大学文学部(歴史学専攻)を経て、1969年 大阪市立大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。 現在 武庫川女子大学名誉教授、博士(臨床教育学)。 今井 良一(いまい りょういち) 1972年 神戸市に生まれる。 1992年 京都大学農学部農林経済学科入学。 2004年 同大学院農学研究科生物資源経済学専攻博士後期課程満期退学。 (副専攻領域)「環境問題および環境教育」を選択。 2007年 博士(農学。京都大学) 現 在 (2010年~)神戸親和大学通信教育部非常勤講師(地理学)。 (2014年9月~)関西学院大学教職教育研究センター非常勤講師(環境教育論)。 関西国際大学基盤教育機構非常勤講師(環境と生活)。 (2023年~)明石工業高等専門学校非常勤講師(科学技術と環境)。 〈専門分野〉近代日本経済史、日本近現代史・東洋史、環境教育学、地理学 |
|
発刊日 |
||
2024年9月1日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-110-7
|
||
 |
忘れられた作曲家テオドール・デュボワ —人類学から見たフランス近代音楽史— 吉岡政德 フォーレやラヴェルが新しい時代を切り開いた陰で忘れられていった作曲家テオドール・デュボワ、今再評価が進み再び歴史の表舞台へ |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
吉岡政德(よしおか まさのり) 1951年生まれ。奈良市出身。東京都立大学大学院社会科学研究科単位取得退学。社会人類学、音楽人類学専攻、東京都立大学人文学部助手、信州大学教養部助教授、神戸大学大学院国際文化学研究科教授、放送大学兵庫学習センター客員教授を経て、現在神戸大学名誉教授。社会人類学博士。 主な著書として、『メラネシアの位階階梯制社会―北部ラガにおける親族・交換・リーダーシップ』(1998年、風響社、第15回大平正芳記念賞受賞)、『反・ポストコロニアル人類学―ポストコロニアルを生きるメラネシア』(2005年、風響社)、The Story of Raga—David Tevimule’s Ethnography on His Own Society, North Raga of Vanuatu.(2013年、The Japanese Society for Oceanic Studies)、『ゲマインシャフト都市―南太平洋の都市人類学』(2016年、風響社)、『豚を殺して偉くなる―メラネシアの階梯制社会におけるリーダーへの道―』(2018年、風響社)など。編著などに、『社会人類学の可能性Ⅰ 歴史のなかの社会』(1988年、弘文堂、共編)、『オセアニア3 近代に生きる』(1993年、東京大学出版会、共編)、『オセアニア学』(2009年、京都大学学術出版会、監修)、『南太平洋を知るための58章 メラネシア、ポリネシア』(2010年、明石書店、共編)がある。 |
|
発刊日 |
||
2024年8月26日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-092-6
|
||
 |
奄美染織史
茂野幽考
幻の名著の復刻 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
茂野 幽考(しげの ゆうこう) 明治二十九年(一八九六)、鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋生。本名茂野榮良。 先祖は代々津口横目(港の役人)として漂着船の検問に当たった。 明治四十五年(一九一二)、古仁屋高等小学校卒業後に上京。 大正二年(一九一三)、東京工科学校入学。大正十年に中南米の民族文化研究のために 渡米、同十二年三月二十日帰国、九月一日に関東大震災に遭い九死に一生を得て帰郷する。以後三年をかけて奄美の島々を廻って古俗や方言・俗信などを調べて、『奄美大島民族史』として完成させた。また、瀬戸内町出身のロシア文学者昇曙夢を介して柳田國男を知り、柳田國男の紹介で岡書院からこの本を出版した。 柳田國男は東京の砧村の書庫の新築落成祝に知名の学者三十人を招き、同書の出版記念を兼ねて赤飯を炊いて祝い、「君は生涯をかけて島の研究をしなさい」と激励してくれた。このとき、折口信夫・伊波普猷・金田一京助・中山太郎・早川孝太郎・宮本常一らが列席、特に沖縄出身の言語学者で民俗学者である伊波普猷とは親交を深めている。 昭和六年(一九三一)京都大学人類学清野教室の三宅宋悦と奄美大島北部の古墳人骨の調査、翌七年には大島全域の婦人の入墨の調査をして百四枚を採取。 昭和十年(一九三五)、上京して東京市役所社会局に奉職 昭和十八年(一九四三)、鹿児島市長の招きにより鹿児島市の郷土課次長。 昭和二十年(一九四五)、鹿児島県立図書館に奉職、戦後は奉仕課長として県下全域を駆け巡って民俗調査をも行った。 右は『日本民俗誌体系』からの転載であるが、行詰めで記してあるので分かり易いように書き替えてある。左は私が編んだ後年の略歴である。 昭和二十六年(一九五一)五十五歳、『日南切支丹史』をヴエリタス書院より出版。(上智大学ヨハネス・ラウレス師により外国に紹介された。) 昭和三十年(一九五五)五十九歳、「古典に生きる郷土・奄美大島」を雑誌『教育技術・中学国語』に掲載 昭和三十一年(一九五六)六十歳、定年退職。自宅を『奄美文化研究所』とする。「初期切支丹の布教と南蛮貿易」を雑誌『教育技術・社会科研究』に掲載 昭和三十三年(一九五八)六十三歳、文化映画『大島紬』の製作に協力 昭和三十五年(一九六〇)六十四歳、『奄美万葉恋歌秘抄』を昭森社から出版、宝文館の『切支丹風土記』の第一巻 九州編「薩摩の切支丹」を担当、「奄美萬葉について」を南日本新聞に連載 昭和三十五年(一九六〇)十一月三日 地方文化に貢献したとして、第十三回南日本文化賞(学術部門)を受賞 昭和三十六年(一九六一)六五歳、第十二回キリスト教史学会(近江八幡市で開催)、「薩摩の切支丹について」を発表 昭和四十二年(一九六七)七十一歳、メキシコ国立自治大学東洋研究所長であるクノート・ロータ氏の訪問を受ける。 昭和四十四年(一九六九)七十三歳、九州学院大学講師・歴史学担当、奄美の古代染織に付いて調査(前述) 昭和四十八年(一九七三)七七歳、『奄美染織史』(奄美文化研究所) 昭和五十一年(一九七六)八十歳、『南島今昔物語』(国書刊行会)。「染織と生活』」第十三号に、「奄美染織考―原始宗教ノロ神に発した奄美の染織文化について」を掲載。「日南切支丹史」を『南日本切支丹史』と改題して、国書刊行会より出版。 昭和五十三年(一九七八)八十二歳、『大島紬の染めと織り』(奄美文化研究所) 昭和五十四年(一九七九)八十三歳、戯曲『嶋の西郷と愛加那』(奄美文化研究所) 昭和六十二年(一九八七)九十一歳、七月二十日に老衰のため死去 |
|
発刊日 |
||
2024年1月16日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-061-2 |
||
 |
一三人の作家 藤村・草平・弥生子・らいてう・勇・和郎・捷平・葦平など
原武 哲
一三人の作家〈島崎藤村・森田草平・野上豊一郎・野上弥生子・平塚らいてう・吉井勇・広津和郎・木山捷平・火野葦平・野田宇太郎・牛島春子・嘉陽安男・帚木蓬生〉の生き様、故郷への思い、漱石との接点、野田宇太郎宛書簡、作品論、作家論、国際学会発表論文、対談等。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3520円(税込) |
原武 哲(はらたけ さとる) 1932年5月14日福岡県大牟田市生まれ。 九州大学文学部国語国文学科卒業。 福岡女学院短期大学国文科助教授、教授を経て、1994年1年間中国・吉林大学外国語学院日語系客員教授、福岡女学院大学人間関係学部教授。現在、福岡女学院大学名誉教授。 主な著書 『夏目漱石と菅虎雄―布衣禅情を楽しむ心友―』(教育出版センター、1983年12月)。『喪章を着けた千円札の漱石―伝記と考証―』(笠間書院、2003年10月)。『夏目漱石の中国紀行』(鳥影社、2020年10月)。『夏目漱石は子役チャップリンと出会ったか?-漱石研究蹣跚―』(鳥影社、2022年4月)。編著に『夏目漱石周辺人物事典』(笠間書院、2014年7月)。 『夏目漱石外伝―菅虎雄先生生誕百五十年記念文集―』(菅虎雄先生顕彰会、2014年10月19日)など。 |
|
発刊日 |
||
2024年1月1日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-018-6 |
||
 |
少女たちの〈居場所〉ー資本の他者としてー
関谷 由美子
「大人に成るは嫌やなこと」(「たけくらべ」) |
|
価格 |
著者略歴 | |
3520円(税込) |
関谷由美子(せきや ゆみこ) 東京生まれ 博士(文学) 1980年 東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程修了 2014年 学位取得(首都大学東京) 職歴 文教大学、大東文化大学、上智大学、共立女子大学、国士舘大学、成城大学短期大学部などで講師を務める。 現在 日本近代文学会、日本文学協会、社会文学会、島崎藤村学会会員 ○著書 『漱石・藤村〈主人公の影〉』(愛育社 1998・5) 『〈磁場〉の漱石―時計はいつも狂っている―』(翰林書房2013・3) ○共著他 『大石修平 感情の歴史』(共編 有精堂1996・10)、『明治女性文学論』(共編 翰林書房2007・11)、『大正女性文学論』(共編 翰林書房2010・12)、『韓流サブカルチュアと女性』(共著 至文堂2006・7)、『井上ひさしの演劇』(共著 翰林書房2012・12)、『つかこうへいの世界 消された〈知〉』(2019・2)、『宝塚の21世紀―演出家とスターが描く舞台』(共著 社会評論社2020・4)など。 |
|
発刊日 |
||
2023年12月25日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-043-8 |
||
 |
鷗外と『ファウスト』ー近代・時間・ニヒリズム
田中岩男
洋の東西で初期近代を生きた鷗外とゲーテ |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
田中岩男(たなか いわお) 1950年、北海道に生まれる。 1973年、弘前大学人文学部文学科(ドイツ文学専攻)卒業。 1975年、東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程(ドイツ文学専攻)修了。 同年、母校の弘前大学人文学部に助手として採用され、講師、助教授、教授を経て 2016年、定年により退職。 現在、弘前大学名誉教授。 著書・論文 『ゲーテと小説―「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」を読む』(郁文堂、1999年)、『エルンテ〈北〉のゲルマニスティク』(編著、郁文堂、1999年)。 『「ファウスト」研究序説』(鳥影社、2016年)、同書により第15回日本独文学会賞(日本語研究書部門)受賞。 論文「〈病める王子〉の快癒―『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』試論」(『ゲーテ年鑑』第31巻、1989年)により日本ゲーテ賞受賞。 |
|
発刊日 |
||
2023年12月13日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-051-3
|
||
 |
日本語文法の科学 ―定本『新文体作法』―
齋藤紘一
日本語文法を新たな視点から見直し、実践的に有効な形で理論的体系づけを図る |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
齋藤 紘一(さいとう こういち) 1943年、群馬県生まれ。東京大学理学部化学科卒。通産省入省後、課長・審議官を務める。 1993年退官後、ISO(国際標準化機構)日本代表委員、独立行政法人理事長等をへて現在、翻訳家。 著 書 『「新文体作法」序説―ゴーゴリ「肖像画」を例に―』(鳥影社、2018年) 『「新文体作法」本説―日本語のルールを知る―』(鳥影社、2021年) 訳 書 フョードル・ソログープ 『小悪魔』(文芸社、2005年) ボリス・ワジモヴィチ・ソコロフ 『スターリンと芸術家たち』(鳥影社、2007年) ワシーリー・グロスマン 『人生と運命』(全3巻、みすず書房、2012年)日本翻訳文化賞受賞 同書 新装版(全3巻、みすず書房、2022年) 『万物は流転する』(みすず書房、2013年) 同書 新装版(みすず書房、2022年) 『システィーナの聖母』(後期作品集、みすず書房、2015年) |
|
発刊日 |
||
2023年9月18日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-039-1
|
||
 |
メスメリズム —磁気的セラピー—
フランツ・アントン・メスマー 著
催眠学、暗示療法の祖、メスマーの生涯と学説。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
〈著者紹介〉 フランツ・アントン・メスマー(Franz Anton Mesmer, 1734-1815) オーストリアの医師。ウィーン大学で医学を修め、『人体への惑星の影響について』(1766)という博士論文を提出した。宇宙には磁気が偏在するという仮説のもとに「動物磁気」説を提唱。ウィーンやパリで行った治療は暗示療法の先駆けと考えられ、後にメスメリズムと呼ばれるようになった。 〈編者・英語訳者紹介〉 ギルバート・フランカウ(Gilbert Frankau, 1884-1952) イギリスの小説家。パブリック・スクールの名門イートン・コレッジ卒業。第一次世界大戦で出征し前線で戦った。第2次世界大戦でも従軍。 作品はLove Story of Aliette Brunton(1922)、映画化されたChristopher Strong(1932)、Royal Regiment(1938)、World without End (1943)、Michael’s Wife (1948)など、多数ある。 〈日本語訳者紹介〉 広本勝也(ひろもと かつや) 慶應義塾大学大学院博士後期課程満期退学。 現在、慶應義塾大学名誉教授。専門は米英の詩と演劇全般。 〈論文〉「仮面劇の起源と原型」(植月恵一郎編『英文学のディスコース』北星堂書店、2004)、「正岡子規とH. Spencer──『文体の哲学』について」(『比較文化研究』No. 98、2011)、「シルヴィア・プラス──軽薄と絶望」(『慶應義塾大学日吉紀要:英語英米文学』No. 61、2012)、他。 |
|
発刊日 |
||
2023年3月31日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-010-0
|
||
 |
『ブッデンブローク家の人々』─ 『悲劇の誕生』のパロディとして
別府陽子
〝トーマス・マン研究に新たな地平をひらく〟 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
別府 陽子(べっぷ ようこ) 1980年関西学院大学文学部ドイツ文学科卒業。 2012年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程ドイツ文学専攻単位取得退学。 大阪大谷大学、京都産業大学非常勤講師。 |
|
発刊日 |
||
2023年3月19日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-014-8
|
||
 |
長期化・重症化させない! 新型コロナ後遺症に向き合う
和田 邦雄
コロナ後遺症1500人以上の患者を直接診療治療してきた、第一線の医師による本質に迫る待望の一冊。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2145円(税込) |
和田邦雄(わだ くにお) 医療法人 邦徳会 邦和病院 理事長・院長。 昭和22年生、富田林市出身、大阪府立天王寺高校卒業、奈良県立医科大学卒業。 奈良県立医大第2外科(現脳神経外科)、大阪府松原市立松原病院外科・整形外科、大阪府立病院(現大阪府急性期総合医療センター)脳神経外科、救命救急センター診療主任を経て邦和病院設立。 日本救急医学会専門医、日本外科学会専門医、日本抗加齢医学会専門医、日本臨牀内科医会認定医、麻酔科標榜医、身体障害者手帳指定医、日本脳神経外科学会員、日本脳卒中学会員、日本脳卒中協会員、日本脳卒中の外科会員、日本神経外傷学会員、日本整形外科会員、日本骨折治療学会員、日本外傷学会員、日本糖尿病協会登録医、日本ヘリコバクター学会認定医、日本ハイパーサーミア学会員、日本抗菌化学療法認定医、日本職業・災害医学会認定労災補償指導医等。奈良医大脳神経外科同門会員。大阪大学特殊救急部(現大阪大学高度救命救急センター)同窓会員。 作曲家(ジャンルは医療と同様にいろんな分野にわたる。クラシック、映画音楽、歌謡曲、演歌、行進曲、校歌など何でも。ユーチューブ:和田邦雄 創作音楽で1000曲以上) 中川 学(なかがわ まなぶ) 医療法人 邦徳会 邦和病院 副院長。 1982年 関西医科大学卒業 1984年 和歌山県国保古座川病院(外科整形外科) 1990年 関西医科大学 大学院博士課程修了 (医学博士) 1995年 医療法人沖縄徳洲会 神戸徳洲会病院外科部長 (外科学会・消化器外科学会:認定医・専門医・指導医) 1998年 関西医科大学第一外科講師 2000年 和歌山県海南市 琴仁会 石本病院副院長(血液浄化療法に携わる) 2008~2014年 大阪府内科医会 臨床内科推薦医 2015年 大阪府堺市 邦徳会 邦和病院(副院長)(救急医療・脳疾患・整形外科疾患に携わる) 2020年新型コロナ感染症に取り組む 外科一般・麻酔標榜医・血液浄化療法(HD/CHDF~ECMO)・NST医師・産業医 得意分野 内視鏡検査(気管支・消化管・膀胱等)・胸腹腔下手術 著書:臨床を科学するシリーズ コロナを知って知識武装 |
|
発刊日 |
||
2023年1月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86782-005-6
|
||
 |
民族学・考古学の目で感じる世界 —イスラエルの自然、人、遺跡、宗教— 平川 敬治
民族・文化・宗教の巨大な交差点 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
平川敬治(ひらかわ けいじ) 1955年福岡生まれ。九州大学教育研究センター講師他、社会人学習講座の講師などを歴任。考古学・地理学・民族学を専攻し、自ら足を運ぶことをモットーに地域の香りのする総合的な比較文化の構築を目指す。主なフィールドは日本を含めた東アジア、西アジア、ヨーロッパで調査を続行中。1983年よりイスラエルで調査を続ける。 主な著書 『考古学による日本歴史』(共著、雄山閣出版、1996年)、『カミと食と生業の文化誌』(創文社、2001)、『遠い空 國分直一、人と学問』(共編海鳥社、2006)、『エン・ゲブ遺跡』(共著、LITHON、2009)、『魚と人をめぐる文化史』(弦書房、2011)、『タコと日本人』(弦書房、2012)、『魚食から文化を知る』(鳥影社、2020)など。 |
|
発刊日 |
||
2023年1月26日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-991-0
|
||
 |
うたはなぜ滅びないのか 進化、認知、シェイクスピアのソネット
ブライアン・ボイド 著
人がこの世にある限り、詩は生き続けるのだ。 |
|
価格 |
訳者略歴 | |
4180円(税込) |
小沢茂(おざわ しげる) 1977年名古屋市生まれ。 2005年名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。 現在愛知淑徳大学教授。 著書 The Poetics of Symbiosis: Reading Seamus Heaney’s Major Works(三恵社) 『共生の詩学』(三恵社) 訳書 ヒーニー『トロイの癒し』(国文社) ヒーニー『詩の矯正』(国文社) ヒーニー『テーベの埋葬』(国文社) コーコラン『シェイマス・ヒーニーの詩』(国文社) オブライエン『カントリー・ガール』(国文社) ボイド『ストーリーの起源』(国文社) クラーゼン『ホラーは誘う』(風媒社) |
|
発刊日 |
||
2022年12月28日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-986-6
|
||
 |
メタ認知能力を育成する授業づくり スコットランドの実践を基にした具体的方法
ピーター・タラント/デボラ・ホルト 著
子どもたちが自ら積極的に学習に取り組むようになるには、どのような授業が必要か。 |
|
価格 |
訳者略歴 | |
1980円(税込) |
日下智志(くさか さとし) 鳴門教育大学院学校教育研究科グローバル教育コース講師。東京学芸大学教育学部卒、University of Leeds, Faculty of Social Sciences, Education and Development course 修士課程修了、広島 大学大学院国際協力研究科博士課程後期修了、博士(教育学)。 学校法人岩田学園ニューインターナショナルスクールオブジャ パン教員、教育コンサルタント(国際協力機構 JICA が開発途 上国で実施する教育プロジェクトに従事)を経て現職。専門分 野は、算数・数学教育学、国際教育開発論。 主要著作 『新しい算数教育の理論と実践』(共著、ミネルヴァ書房、2021 年) |
|
発刊日 |
||
2022年12月18日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-983-5
|
||
 【試し読みする】 |
人新世の絶滅学 人類・文明絶滅の思弁的空無実在論
星野克美
私たちは人類の絶滅というとんでもない状況下にある。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3850円(税込) |
星野克美(ほしの かつみ) 多摩大学名誉教授 1940年名古屋市生まれ、名古屋大学経済学部卒業 研究履歴:筑波大学社会工学系専任講師・助教授、多摩大学経営情報学部教授・多摩大学大学院経営情報学研究科教授を経て、現職 学会:比較文明学会会員、地球システム・倫理学会会員 専攻:絶滅学、文明哲学、地球環境文明論 主著:「地球環境文明論」(ダイヤモンド社)、「社会変動の理論と計測」(東洋経済新報社)、「消費人類学」(東洋経済新報社)、「流行予知科学」(PHP研究所)など多数 学術論文:「工業文明崩壊後の超生命文明の構想」(比較文明学会『比較文明』)、「工業文明の崩壊後に、人類はどういう文明で生存できるか」(『収奪文明から環流文明へ』、東海大学出版会)など多数 学会発表:「現代文明滅亡の検証と考察」(第33回比較文明学会大会)、「文明崩壊と農耕回帰文明の構想」(第12回地球システム・倫理学会学術大会)、「生存文明・残存文明の展望」(第35回比較文明学会大会)、「人新世文明論」(第37回比較文明学会大会)、「人新世時代の思弁的非在論」(第38回比較文明学会大会)、「地球気候力動性の絶滅哲学――地球気候体実在論と人類絶滅」(第39回比較文明学会大会) 創作:絶滅形而上詩、人工物フォトアート |
|
発刊日 |
||
2022年11月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-999-6
|
||
 |
高校生と文学作品を読む
藤本英二
ことばの本源的な力とは何か? 豊富な実践例から文学教育の意義を明らかにし、最近の国語教育論議に一石を投じる書。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
藤本英二(ふじもと えいじ) 1952年愛媛県松山市に生まれる。 神戸大学文学部卒業後、兵庫県立高校で、国語教師として勤務する。学生時代、自主ゼミ運動にかかわり、その後民間教育研究運動に参加。兵庫文学教育の会、高山智津子・文学と絵本研究所で活動。 著書 『ことばさがしの旅─国語表現の試み』上・下、『現代詩の授業』、『読むこと書くこと 大人への回路』、『聞かしてぇ〜な仕事の話 聞き書きの可能性』、『読みきかせに始まる 絵本から『サラダ日記』まで』、『児童文学の境界へ 梨木香歩の世界』、『物語のかなた 上橋菜穂子の世界』、『人気のひみつ、魅力のありか 21世紀こども文学論』などがある。 |
|
発刊日 |
||
2022年9月1日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-979-8
|
||
 |
ドストエフスキー『悪霊』の概要展望と深層構造 —悪魔のヴォードヴィル的空間— 清水孝純
われわれは今、「悪魔の黙示録」の世界を生きているのか? ドストエフスキー生誕200年をすぎて、21世紀の今日また切実さをもって甦る名作を、長年ドストエフスキー研究・比較文学に携わってきた第一人者が徹底解析する。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2750円(税込) |
清水孝純(しみず たかよし) 1930年東京生まれ。東京大学大学院比較文学比較文化博士課程を修了後、日本大学講師を経て、1969年九州大学教養部助教授。1976年同教授。同大学退職後、福岡大学人文学部教授を経て、現在九州大学名誉教授。 主な著書 『小林秀雄とフランス象徴主義』(審美社 1980) 『ドストエフスキー・ノート 『罪と罰』の世界』(九州大学出版会、第1回池田健太郎賞受賞 1981) 『西洋文学への招待 中世の幻想と笑い』(九州大学出版会 1982) 『祝祭空間の想像力 ヨーロッパ中世文学を読む』(講談社学術文庫 1990) 『幻景のロシア ペレストロイカの底流』(九州大学出版会 1991) 『漱石 その反オイディプス的世界』(翰林書房 1993) 『道化の風景 ドストエフスキーを読む』(九州大学出版会 1994) 『交響する群像(『カラマーゾフの兄弟』を読む 1)』(九州大学出版会 1998) 『漱石そのユートピア的世界』(翰林書房 1998) 『闇の王国・光の王国(『カラマーゾフの兄弟』を読む 2)』(九州大学出版会 1999) 『新たなる出発(『カラマーゾフの兄弟』を読む 3)』(九州大学出版会 2001) 『笑いのユートピア 『吾輩は猫である』の世界』(翰林書房、第11回やまなし文学賞受賞 2002) 『ルネサンスの文学 遍歴とパノラマ』(講談社学術文庫 2007) 『白痴』を読む』(九州大学出版会 2013、第13回日本キリスト教文学会賞受賞) 『漱石『夢十夜』探索―闇に浮かぶ道標』(翰林書房 2015) その他論文多数 |
|
発刊日 |
||
2022年8月26日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-977-4
|
||
 |
ヘーゲルのイエナ時代 完結編 —『精神の現象学』の誕生—
松村健吾
『精神の現象学』の誕生を、初版に見られる8ヶ所の無意味な一行の空白を手がかりに読み解く。設計の変更による歪みを矯正する足場を再現し、建築現場に迫る。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
6600円(税込) |
松村 健吾(まつむら けんご) 1947年、愛媛県の弓削島に生まれ、同地の小中学校、今治西高、埼玉大学を経て、東京都立大学大学院博士課程単位取得退学 博士(社会学、一橋大学) 大東文化大学名誉教授 著書・論文 『初期ヘーゲル論考』(博士論文、2005年) 『革命と宗教―初期ヘーゲル論考―』(近代文芸社、2007年) 『倫理のディアレクティーク』(文化書房博文社、1993,1997,2006年) 『日常哲学派宣言』(文化書房博文社、1997,1999年) 『ヘーゲルのイエナ時代 生活編』(文化書房博文社、2012年) 『ヘーゲルのイエナ時代 理論編』(鳥影社、2019年) その他 |
|
発刊日 |
||
2022年3月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-952-1
|
||
 |
ゲーテの苦悩 ―『親和力』に込めた理念とは― 田村和子
ゲーテが苦しんだ理性と感性との葛藤。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
田村 和子(たむら かずこ) 1940年大阪府生まれ お茶の水女子大学文教育学部哲学科卒 早稲田大学第一文学部文学科ドイツ文学専修学士卒 同大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻博士後期課程修了 日本独文学会、日本ゲーテ協会会員 『ふみよむつきひ』(鳥影社) |
|
発刊日 |
||
2022年1月26日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-901-9
|
||
 |
新訳 金瓶梅 中巻
田中智行 訳
「リズムよく読める」「想像力が刺激される」と話題の上巻につづき |
|
価格 |
訳者略歴 | |
3850円(税込) |
田中 智行(たなか ともゆき) 1977年、横浜生まれ。 2000年、慶應義塾大学文学部卒業。 2011年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。 日本学術振興会特別研究員(PD)、徳島大学准教授を経て、 現在、大阪大学大学院言語文化研究科准教授。 専門は中国古典文学(白話小説)。 主な著書に、 『とびらをあける中国文学』(共著、新典社、近刊) 主な論文に、 「『金瓶梅』第三十九回の構成」(『東方学』第119輯、2010) 「『金瓶梅』張竹坡批評の態度」(『東方学』第125輯、2013)などがある。 |
|
発刊日 |
||
2021年9月22日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-918-7
|
||
 |
『新文体作法』本説 ―日本語のルールを知る― 齋藤紘一
より正確に、より分かり易く伝えるために |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
齋藤 紘一(さいとう こういち) 1943年、群馬県生まれ。 東京大学理学部化学科卒。 通産省入省後、課長・審議官を務める。 1993年退官後、ISO(国際標準化機構)日本代表委員、 独立行政法人理事長等をへて現在、翻訳家。 著 書 『「新文体作法」序説 ―ゴーゴリ「肖像画」を例に― 』(鳥影社、2018年) 訳 書 フョードル・ソログープ 『小悪魔』(文芸社、2005年) ボリス・ワジモヴィチ・ソコロフ 『スターリンと芸術家たち』(鳥影社、2007年) ワシーリー・グロスマン 『人生と運命』(全3巻、みすず書房、2012年)日本翻訳文化賞受賞 『万物は流転する』(みすず書房、2013年) 『システィーナの聖母』(後期作品集、みすず書房、2015年) |
|
発刊日 |
||
2021年9月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-909-5
|
||
 |
光と影 ハイデガーが君の生と死を照らす!
村瀬 亨
今だからこそ考えてみる“生きるってことを” |
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
村瀬 亨(むらせ とおる) 河合塾講師、河合文化教育研究所研究員。早大・東大大学院で国際政治を修め、ハワイ大学大学院へ留学したのち、岐阜教育大学&付属高校(現・岐阜聖徳学園大学)、神奈川大学などの講師を経て、河合塾専任講師となる。 主な著者として『Top Grade 難関大突破 英語長文問題精選』(学習研究社)、共著に『英語長文読解 読み方から解法まで [発展編] 』(河合出版)、『ENGLISH BOOSTER 大学入試英語スタートブック』(学研プラス)、訳書にウィリアム W・カウフマン著『1980年代の防衛』(カヨウ出版)など多数。 インターネット配信「学びエイド」で入試問題解説や各大学教授との対談を配信中。 |
|
発刊日 |
||
2021年8月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-916-3
|
||
 |
静けさ、安らぎ、喜び、そして自然 ティーク文学とアインザームカイト 山縣光晶 ドイツロマン主義文学の代表的文豪であるルートヴィヒ・ティーク。 本書は、ティークの作品を通じてアインザームカイトのもつ多様で重層的な意味合いを探求する。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2200円(税込) |
山縣 光晶(やまがた みつあき) 1950年生まれ。 ドイツ環境政策研究所所長、林業経済研究所フェロー研究員。 1972年、東京農工大学農学部卒業。 2013年、上智大学大学院文学研究科(ドイツ文学専攻)博士後期課程修了。 博士 (文学) 。 林野庁国有林野総合利用推進室長、近畿中国森林管理局計画部長、岐阜県立森林文化アカデミー教授、東京農工大学・京都精華大学・上智大学講師、林道安全協会専務理事、全国森林組合連合会常務理事、一般財団法人林業経済研究所所長などを歴任。 日本独文学会会員。 専門はドイツロマン主義文学、環境問題。 『原子力と人間』、『木材と文明』、『森なしには生きられない―ヨーロッパ・自然美とエコロジーの文化史』、『森が語るドイツの歴史』(築地書館)などの訳書、著書がある。 |
|
発刊日 |
||
2021年8月24日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-922-4
|
||
 |
藤本卓教育論集 –〈教育〉〈学習〉〈生活指導〉– 藤本 卓
子どもは、大人に教育されるだけでは育たない。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3960円(税込) |
藤本 卓(ふじもと たかし) 1950年兵庫県生まれ。 大東文化大学文学部教育学科名誉教授。 70年代初め、神戸大学教育学部で、自主ゼミナール運動のリーダーとして活動。 東京大学大学院教育学研究科へ進み、教育哲学を専攻する(博士課程単位取得満期退学)。 80年代半ばから全国高校生活指導研究協議会の常任委員として精力的に活躍し、〈教育のレトリック〉、〈世代の自治〉論などを提唱した。 1992年より大東文化大学に勤務、大学教育実践家として、学生たちに公開ゼミ、映画会、講演会などを企画・運営させることを続ける。 日本教育学会、日本生活指導学会、全国高校生活指導研究協議会(常任委員)。 共著に『学校の再生をめざして』1巻、3巻(東京大学出版会、1992年)、 編著に『登校拒否・不登校』(一葉書房、1993年)、『公論よ起これ! 「日の丸」「君が代」』(太郎次郎社、1999年)、 翻訳書にウェンディ・ウォラス著『あきらめない教師たちのリアル ロンドン都心裏、公立小学校の日々』(太郎次郎社エディタス、2009年)などがある。 2020年3月逝去。 |
|
発刊日 |
||
2021年5月25日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-886-9
|
||
 |
ゲーテにおける生命哲学の研究
岸・ツグラッゲン・エヴェリン
あなたの知らなかったゲーテ。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
岸・ツグラッゲン・エヴェリン(Evelyn Kishi-Zgraggen) 1975年スイス・チューリッヒ生まれ。 チューリッヒ大学文学部出身。 創価大学大学院文学研究科博士課程修了(人文学博士)。 ゲーテの生命哲学の研究にはじまり、ゲーテと東洋思想の比較思想的研究、ドイツ文学と日本文学の比較文学的研究までその研究対象は広い。 |
|
発刊日 |
||
2021年5月2日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-891-3
|
||
 |
モーリッツとその同時代人たち —ドイツ啓蒙主義・古典主義・初期ロマン主義 山本惇二
わが国で未開拓の研究領域に果敢に挑戦した労作 |
|
価格 |
||
5940円(税込) |
||
発刊日 |
||
2021年1月18日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-856-2
|
||
 |
アナイス・ニンとの対話 ―インタビュー集―
アナイス・ニン研究会 訳
フェミニズム運動の先駆者 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
アナイス・ニン(1903年─1977年) スペイン人作曲家を父に、デンマーク系フランス人歌手を母として、パリ郊外ヌイイ・シュル・セーヌに生まれる。11才の時ニューヨークに移住。20代の時夫とパリに住み作家修行を始める。戦火を避けて1939年にニューヨークに戻り、その後アメリカにとどまった。 ヘンリー・ミラー、アントナン・アルトー、オットー・ランクほか作家・芸術家たちとの交遊、恋愛、そして作家としての葛藤を一生涯に渡り綴った膨大な日記で有名。小説は『人工の冬』『炎へのはしご』『信天翁の子供たち』『ミノタウロスの誘惑」などの著書がある。 |
|
発刊日 |
||
2020年12月21日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-818-0
|
||
 |
夏目漱石の中国紀行
原武 哲
漱石は英国留学途中に寄港した上海・香港、後年の満韓旅行で中国に何を見たのか? |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
原武 哲(はらたけ さとる) 1932年5月14日福岡県大牟田市生まれ。 九州大学文学部国語国文学科卒業。 福岡女学院短期大学国文科助教授、教授を経て、1994年1年間中国吉林大学外国語学院日語系客員教授、福岡女学院大学人間関係学部教授。現在、福岡女学院大学名誉教授。 主な著書 『夏目漱石と菅虎雄―布衣禅情を楽しむ心友―』(教育出版センター、1983年12月)、『喪章を着けた千円札の漱石―伝記と考証』(笠間書院、2003年10月)。編書に『夏目漱石周辺人物事典』(笠間書院、2014年7月)、『夏目漱石外伝―菅虎雄先生生誕百五十年記念文集―』(菅虎雄先生顕彰会、2014年10月19日) など。 |
|
発刊日 |
||
2020年10月16日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-815-9
|
||
 |
超人と永遠回帰のための『ツァラトゥストラ』全訳注・講義
小山修一 『ツァラトゥストラ』に関して多くの書籍を送り出してきた著者による、渾身の全訳注と講義。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3960円(税込) |
小山修一(こやましゅういち) 1948年 福岡県生まれ。 1972年 西南学院大(法)卆、(株)マルエツ等を経て 1983年 中央大学大学院文学研究科独文専攻博士後期課程修了。 1987年 独語通訳免許取得、 1989年4月から2012年3月まで石巻専修大学経営学部准教授。 元『文芸東北』同人 主著・ 『ニーチェ「ツァラトゥストラ」を少し深読みするための十五章』(鳥影社2013) 『根本思想を骨抜きにした「ツァラトゥストラ」翻訳史―並びに、それに関わる日本近代文学』(鳥影社2018) 訳書・ 『ツァラトゥストラ』上(鳥影社2002) 『ツァラトゥストラ』下(鳥影社2003) 『黄金の星はこう語った』上(鳥影社2011) 『黄金の星はこう語った』下(鳥影社2011) 2018改訂『黄金の星はこう語った』(鳥影社2018) ※訳書の原典は三度とも Kroner版 Also Sprach Zarathustra | |
発刊日 |
||
2020年5月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-820-3 |
||
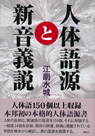 |
人体語源と新音義説
江副水城
人体語150個以上収録 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2640円(税込) |
江副 水城(えぞえ みずき) 1938年熊本県八代市生まれ。 東京大学法学部卒、上場企業(旭化成)に勤務後退職。 趣味は麻雀愛好、動植物観察、言語研究。 著 書:『魚名源』(2009年5月)『鳥名源』(2010年6月)『獣名源』(2012年10月)『蟲名源』(2014年2月) 発行所 株式会社パレード、発売所 株式会社星雲社 『草木名の語源』(2018年7月)株式会社鳥影社 |
|
発刊日 |
||
2020年5月12日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-788-6
|
||
 |
日本の臨床現場で専門医が創る 図解 精神療法 広岡清伸
“日本発"心の病の捉え方と治し方 |
|
価格 |
著者略歴 | |
13200円(税込) |
広岡清伸(ひろおか・きよのぶ) 精神科専門医、指導医。 精神保健指定医。 元臨床心理士、元日本医師会認定産業医、元ケアマネージャー。 富山県出身、高岡高校卒、早稲田大学中退、日本大学医学部卒。 東京大学医学部附属病院精神科研修医、堀ノ内病院、関東労災病院などを経て、 1992年横浜市港北区に広岡クリニックを開設。 現在、広岡クリニック院長、理事長。 著書『広岡式 こころの病の治し方』(日経BP) |
|
発刊日 |
||
2020年4月24日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-808-1
|
||
 |
増補改訂版 環境教育論 —現代社会と生活環境— 今井清一/今井良一 環境教育は消費者教育。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
今井清一(いまい せいいち) 1938年神戸市に生まれる。 神戸大学文学部を経て、1969年大阪市立大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。 現在、武庫川女子大学名誉教授、元神戸親和女子大学発達教育学部教授、博士(臨床教育学)。 今井良一(いまい りょういち) 1972年神戸市に生まれる。 1992年京都大学農学部農林経済学科入学。 2004年同大学院農学研究科生物資源経済学専攻博士後期課程満期退学。 2007年博士(農学、京都大学)。 現在(2010年~)神戸親和女子大学発達教育学部・通信教育部非常勤講師(地理学)。 (2014年9月〜)関西学院大学教職教育研究センター非常勤講師(環境教育論)。 関西国際大学基盤教育機構非常勤講師(環境とエネルギー/環境と生活)。 専門分野、日本経済史、歴史学(日本史・東洋史)、環境教育学、地理学(農業地理学) |
|
発刊日 |
||
2020年4月7日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-810-4
|
||
 |
血液型と宗教
前川輝光
ABO式血液型と宗教の関連 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
前川輝光(まえかわ てるみつ) 1954年熊本県生まれ。 大阪外国語大学ヒンディー語科、東京外国語大学大学院地域研究研究科、東京大学大学院人文科学研究科(宗教学・宗教史学)に学ぶ。 1994年中村元賞受賞。1997年東京大学より博士(文学)。 現職:亜細亜大学国際関係学部教授。 専攻:宗教学、インド宗教・文化論。 著書:『マックス・ヴェーバーとインド』(未来社、1992年)、 『血液型人間学―運命との対話』(松籟社、1998年)、 『マハーバーラタの世界』(めこん、2006年)、 『A型とB型―二つの世界』(鳥影社、2011年)、 『マハーバーラタとラーマーヤナ』(春風社、2013年) 『前川教授の人生、血液型。』(春風社、2014年)など。 |
|
発刊日 |
||
2020年3月26日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-809-8
|
||
 |
共感・ピクチャレスク・ポイエーシス —18世紀イギリス美学の諸相— 相澤照明 理性の時代から感性の時代へと移り変わる18世紀イギリスの美学思想を〈共感〉〈ピクチャレスク〉〈ポイエーシス〉という三つの視座から見渡す。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3520円(税込) |
相澤 照明 (あいざわ てるあき) 佐賀大学名誉教授。 専門は18世紀美学・藝術論。 論文: 「悲劇の快について―D・ヒュームの悲劇論とその周辺―」(群馬県立女子大学紀要 1986年) 「エドマンド・バークにおける崇高と恐怖」(『藝術研究』広島藝術学研究会 1991年) 「ジョシュア・レノルズ卿の新時代的感性」(佐賀大学教養部紀要 1994年) 「ピクチャレスクと〈動きと時間〉―プライスのピクチャレスク美学の一断面―」(齋籐稔編『諸藝術の共生』所収 渓水社) 「イギリス経験論における笑い論―知的笑いの分析を中心として―」(佐賀大学教養部紀要 1996年) 「視覚性と言語をめぐって―言語起源論の文脈とウォーバートン―」(『「感性学」の新たな可能性―その意義と限界』(科研報告書 研究代表者 山縣熙)所収 2010年) 「旅の世紀としてのイギリス18世紀―ギルピンのピクチャレスク・ツアーを中心として―」(西村清和編『日常性の環境美学』所収 勁草書房) 翻訳: 『18世紀イギリスのアカデミズム藝術思想―「ジョシュア・レノルズ卿の「講話集」―』(知泉書館)等 |
|
発刊日 |
||
2020年3月16日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-797-8
|
||
 |
微笑む言葉、舞い落ちる散文 —ローベルト・ヴァルザー論 新本史斉
なぜ、ヴァルザーはかくも重要なのか? |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
新本史斉(にいもと・ふみなり) 1964年広島県生まれ。 専門はドイツ語圏近・現代文学。翻訳論。 現在、津田塾大学教授。 訳書: 『ローベルト・ヴァルザー作品集』1巻、4巻、5巻 (鳥影社、2010年、2012年、2015年) イルマ・ラクーザ他編『ヨーロッパは書く』(鳥影社、2008年、共訳) ペーター・ウッツ『別の言葉で言えば』(鳥影社、2011年) イルマ・ラクーザ『もっと、海を』(鳥影社、2018年)他。 |
|
発刊日 |
||
2020年3月5日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-799-2
|
||
 |
日本語を第二言語とする女性配偶者の学習支援に関する研究 ―ライフストーリーによる生と学びのとらえかえし― 久野弓枝
膨大な数の外国人が押し寄せる日本。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
久野 弓枝(くの ゆみえ) 札幌大学教授 教育学博士(北海道大学) 専門分野:日本語教育、留学生教育 所属学会:日本語教育学会、異文化間教育学会、留学生教育学会 主な論文:「自己内省の観点からのライフストーリーの再読について ―留学生の成長をサポートするビジネス日本語教育の実践を目指して―」 『北海道大学大学院教育学研究院紀要』第130号、2018年3月 「中国人編入留学生のキャリア形成に関するライフストーリー研究(3) ―トランジションとagencyに着目して-」 『札幌大学総合論叢』第44号、2017年10月(単著) |
|
発刊日 |
||
2020年2月27日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-795-4
|
||
 |
甲州・樫山村の歴史と民俗III 近世の樫山村・浅川村および「村」成立過程 序 ー「地名考」「文書・御水帳分析」「聞取り調査」からー 大柴弘子 樫山村・浅川村を通して近世の「村」および「村」成立過程をテーマにした序論である。主に文書解読分析結果を一次資料として提示し次の段階の研究資料に繋げるものである。 著者の郷土愛が本書を完成させた。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
大柴弘子(おおしば ひろこ) 1941年生まれる。 1944~1959年、清里村(樫山村)在住。 1962年日本国有鉄道中央鉄道病院看護婦養成所、 1966年埼玉県立女子公衆衛生専門学院、 1977年武蔵大学人文学部社会学科、各卒。 1994-2002年東京都立大学大学院修士課程卒、同大学院博士課程単位取得退学(社会人類学専攻)。 職歴:大宮鉄道病院、佐久総合病院健康管理部および日本農村医学研究所、南相木村、信州大学医療技術短期大学部(看護学)、神奈川県社会保険協会健康相談室、昭和大学保健医療学部兼任講師(医療人類学)、各勤務。社会保険横浜中央看護専門学校、東京女子医科大学看護短期大学、厚生省看護研修研究センター等非常勤講師。 現在、湖南治療文化研究所主幹(保健師、医学博士)。 |
|
発刊日 |
||
2020年1月1日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-773-2
|
||
 |
徳と市場〈普及版〉
折原 裕
食品偽装やクレーマー問題はなぜ起こるのか? |
|
価格 |
著者略歴 | |
1100円(税込) |
折原 裕(おりはら ゆたか) 1951年愛知県生まれ 愛知大学哲学科卒業、武蔵大学大学院修了(経済学博士) 現在、敬愛大学名誉教授 |
|
発刊日 |
||
2019年11月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-767-1
|
||
 |
新版 誤れる現代医学
橋本行生
より深く考える医師と患者のために |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
橋本行生 本籍名 橋本行則(はしもとゆきのり) (略歴) 昭和10年生まれ、本籍熊本県、医学博士。 昭和35年、熊本大学医学部卒、同大学院およびオーストラリア・モナシュ大学で骨格筋・平滑筋の電気生理学の研究、東大医学部物療内科から社会福祉法人毛呂病院(現埼玉医大)第二内科、国立東静病院内科、岩手県衣川村国保診療所を経て、昭和49年より大阪府枚方市で橋本内科医院・みずほ漢方研究所、平成3年より熊本市で橋本行生内科を開設、現在に至る。 (著書) 誤れる現代医学、創元社、昭和46年 病気を直すのは誰か、創元社、昭和49年 あなたこそあなたの主治医、農文協、昭和54年 医者がすすめる民間療法、講談社、昭和54年 自立こそ治癒力の源泉、柏樹社、1979年 治療学への提言、創元社、昭和55年 病気は自分で直す、三一書房、昭和59年 病からのひとり立ち、三一書房、1984年 操体・食・漢方・現代医学 家庭医療事典、農文協、昭和61年 病気を治す着眼点、柏樹社、1988年 医療をささえる死生観、柏樹社、1988年 魂が救われるために、勁草出版サービスセンター、1991年 病いを知り己れを知る、農文協、1994年 いっしょに治るいくつもの病気、農文協、1996年 共著:私こそ私の主治医、 緑風出版、2001年 症例による現代医学の中の漢方診療、医歯薬出版、2003年 新版・あなたこそあなたの主治医、農文協、2003年 病気を直す心意氣、農文協、2004年 共編著:あなたにもできるがんの基礎療法、農文協、2005年 魂が救われるために第六巻、自家出版、平成23年 |
|
発刊日 |
||
2019年8月17日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-760-2
|
||
 |
入門フォーカシング
阿世賀浩一郎
*そもそも、なぜ人は悩みはじめるのか |
|
価格 |
著者略歴 | |
660円(税込) |
阿世賀浩一郎(あせが こういちろう) 1960年9月1日生まれ。 福岡県久留米市出身。個人開業心理カウンセラー。 The International Focusing Institute認定 Focusing Professional 法政大学文学部哲学科卒業 立教大学大学院文学研究科心理学専攻博士前期課程修了 法政大学多摩学生部学生相談室非常勤カウンセラー 明治学院大学学生相談センター常勤カウンセラー 湘南フォーカシング・カウンセリングルーム(個人開業) 故郷久留米市に戻り、現在、久留米フォーカシング・カウンセリングルーム主宰 Skypeを用いての全国からの相談も受け付けている。 著書:『エヴァンゲリオンの深層心理─自己という迷宮─』(幻冬舎) 『フォーカシング事始め』(村瀬孝雄・日笠摩子・近田輝行との共著、金子書房) 『現代のエスプリ』410「治療者にとってのフォーカシング」(伊藤研一との編著、至文堂) |
|
発刊日 |
||
2019年8月17日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-763-3
|
||
 |
ヘーゲルのイエナ時代 理論編
松村健吾
概略的解釈に流されることなくあくまでもテキストを一文字ずつ辿り |
|
価格 |
著者略歴 | |
5280円(税込) |
松村 健吾(まつむら けんご) 東京都立大学大学院博士課程単位取得退学 博士(社会学、一橋大学) 大東文化大学名誉教授 著書・論文:『初期ヘーゲル論考』(博士論文、2005年)『倫理のディアレクティーク』(1993, 1997, 2006年)『日常哲学派宣言』(1997, 1999年)『ヘーゲルのイエナ時代 生活編』(2012年)(以上、文化書房博文社)『革命と宗教─初期ヘーゲル論考─』(近代文芸社、2007年)その他 |
|
発刊日 |
||
2019年7月8日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-754-1
|
||
 |
オットー・クレンペラー 最晩年の芸術と魂の解放 ―1967〜69年の音楽活動の検証を通じて― 中島 仁
20世紀の大指揮者クレンペラーの最晩年の姿を通して人間における音楽のもつ意味を浮かびあがらせる好著である。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2365円(税込) |
中島 仁(なかしま ひとし) 1964年島根県生まれ。 関西学院大学経済学部卒業。 島根県庁に25年間勤めたのち、神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期修了。修士(学術)。 現在、クレンペラーに関する文献の翻訳のほか、アメリカ亡命時代、ハンガリー時代におけるクレンペラーの芸術活動を研究している。 |
|
発刊日 |
||
2019年6月27日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-744-2
|
||
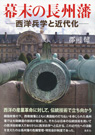 |
幕末の長州藩 西洋兵学と近代化
郡司 健
西洋の産業革命に対して、伝統技術で立ち向かう |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
郡司 健(ぐんじ たけし) 1947年、山口県生まれ。 大阪学院大学経営学部教授 経営学博士(神戸商科大学、〈現〉兵庫県立大学) 公認会計士試験委員(2006年12月〜2010年2月) 著書 『連結会計制度論 —ドイツ連結会計報告の国際化対応—』(中央経済社、2000年、日本会計研究学会太田・黒澤賞受賞) 『国際シンポジウム報告書 海を渡った長州砲 〜長州ファイブも学んだロンドンからの便り〜』(編著、ダイテック社、2007年) 『海を渡った長州砲 —ロンドンの大砲、萩に帰る—』(萩ものがたり、2008年) 『現代会計の基礎と応用』(中央経済社、2019年) 他 |
|
発刊日 |
||
2019年5月18日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-746-6
|
||
 |
新渡戸稲造 人格論と社会観
谷口 稔 日本の「武士道」を近代に活かそうとした思想家であり、敬虔なキリスト教信者でもあった新渡戸稲造。多岐にわたる活動を続けた彼の「人格論」をベースに、「農業思想」「植民思想」「教育思想」を論じて、その思想の解明と、真の人物像に迫る。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
谷口 稔(たにぐち みのる) 恵泉女学園大学人文学部特任教授 1957年 長崎県生まれ。 1981年 慶應義塾大学経済学部卒業。 1983年 慶應義塾大学大学院文学研究科(倫理学)修了。 その後、31年間の恵泉女学園中学・高等学校教諭を経て、 横浜国立大学大学院国際社会科学府博士課程修了。博士(経済学)。 2018年より現職。空手(剛柔流)二段。剣道四段。 |
|
発刊日 |
||
2019年4月3日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-740-4
|
||
 |
反面教師として読んだ『文章読本』
原不二夫
日本語を書くすべての人々に贈る「文章読本」の決定版。作家、教師、編集者、校正者、作文添削者のみならず、およそ文章を書く者すべてにとって、これは必須の一冊となるだろう。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
原 不二夫(はら ふじお) 1943年 長野県生まれ 1962年 諏訪清陵高校卒業 1967年 東京大学経済学部卒業 1967年 アジア経済研究所入所 1999年 南山大学外国語学部教授 2012年 同学部定年退職 マラヤ大学(マレーシア)、アモイ大学(中国)などで客員教員 学位1997年7月学術博士(東京大学総合文化研究科) 著書:『英領マラヤの日本人』アジア経済研究所、1986年(劉暁民訳『英属馬来亜的日本人』厦門大学、2013年)、『文豪を添削する:正確な日本語を求めて』謄光出版、1991年(私家版) |
|
発刊日 |
||
2019年3月28日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-725-1
|
||
 |
五島列島沖合に海没処分された潜水艦24艦の全貌
浦 環
|
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
浦 環(うら たまき) 1948年(昭和23年)生まれ。 一般社団法人ラ・プロンジェ深海工学会 代表理事(2017年1月より) 九州工業大学社会ロボット具現化センター 特別教授(2013年4月より) 東京大学名誉教授(2013年4月より) 1972年、東京大学工学部卒。同工学系大学院船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。 東京大学生産技術研究所講師、助教授を経て1992年より教授。 自律型海中ロボットの研究開発を推進、「r2D4」や「Tuna-Sand」など、 海中工学や海洋科学に貢献する自律型海中ロボットを開発し調査活動をおこなう。 日本造船学会論文賞、日本機械学会技術賞、 IEEE/OES Distinguished Technical Achievement Awardなどを受賞。IEEE Fellow。 高等海難審判庁参審員や総合海洋政策本部参与などを勤め、 海事の安全や我が国の海洋政策に貢献。 主な著書に『海中ロボット総覧』、『大型タンカーの海難救助論』など。 |
|
発刊日 |
||
2019年2月27日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-729-9
|
||
 |
〈改訂増補版〉 詩に映るゲーテの生涯 柴田 翔
華やぐ宮廷、突如、町を走り抜ける貧民の群れ。砲兵士官ナポレオンの権力把握、炎上する皇帝の都モスクワ。そのすべてを凝視する小国家ヴァイマルの宰相、詩人ゲーテ。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
柴田 翔(しばた しょう) 作家、ドイツ文学研究者。 1935(昭和10)年1月 東京生まれ。 武蔵高校から東京大学へ進学、工学部から転じて独文科卒。 1960(昭和35)年 東京大学大学院独文科修士修了、同大文学部助手。 1961(昭和36)年「親和力研究」で日本ゲーテ協会ゲーテ賞。 翌年より2年間、西ドイツ・フランクフルト大より奨学金を得て、留学。 1964(昭和39)年『されどわれらが日々─』で第51回芥川賞。 東大助手を辞し、西ベルリンなどに滞在。帰国後、都立大講師、助教授を経て 1969(昭和44)年4月 東京大学文学部助教授、のち教授。文学部長を務める。 1994(平成6)年3月 定年退官、名誉教授。4月、共立女子大学文芸学部教授。 2004(平成16)年3月 同上定年退職。 |
|
発刊日 |
||
2019年2月4日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-726-8
|
||
 |
ハイネを現代の視点から読む —断章・幻想破壊・食・女性 奈倉洋子
ハイネの眼差しは、常に自らが生きている時代の人々や事象に向けられ、現代という時代をとらえ、それと対峙していた。Ⅰ章の「ハイネ的ロマン主義」では、自らの恋の経験を客体化し、男女の関係を見据え、現代人の恋愛関係をさりげない形で詩にし、民衆的な文学形式を積極的に取り入れ、民衆とコミュニケーションをとろうとした姿勢、Ⅱ章では、従来のような調和的に完結した文学世界は、自分が生きている時代には合わないと考え、文章の書き方そのものを時代に見合ったものにしようと、Fragment形式を自分なりのものにし、開かれた文章スタイルを打ち立てたこと、Ⅲ章の「諷刺の手法」では、あたかも二十一世紀の現在に切り込んでいるかのようなアクチュアルな諷刺詩を書いたこと、Ⅴ章の「ハイネにおける食」では、深遠で高尚な哲学的思索的文学世界を誇る近代ドイツ文学に、日常世界そのものである食を持ち込んだことなどである。Ⅳ章のサロンの問題、またⅥ章の「ハイネと女性たち」によって、理想の女性(像)と本能的嗜好との乖離に見られるようなアンビヴァレントな傾向に焦点を当てる。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
奈倉洋子(なぐら・ようこ) 早稲田大学大学院博士課程修了。 京都教育大学名誉教授。 専門は、ドイツ文学・文化、比較文学・文化。 主要著書:『ドイツの民衆文化 ベンケルザング』(彩流社、1996年) 『日本の近代化とグリム童話』(世界思想社、2005年) 『グリムにおける魔女とユダヤ人─メルヒェン・伝説・神話』(鳥影社、2008年) 『ハイネとその時代』(共著、朝日出版社、1977年) 『ドイツ文化を担った女性たち』(共編著、鳥影社、2008年) |
|
発刊日 |
||
2018年12月13日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-706-0
|
||
 |
スウェーデン王カール十一世の幻視について —奇譚迷宮の散策への誘い— 佐藤恵三
巷間で語りつづけられたこの謎めいた資料は事実なのか、またその真意は何であったのか、その問いに限りなく近づこうとする試み。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2860円(税込) |
佐藤恵三(さとう・けいぞう) 弘前市に生まれる、京都大学ドイツ語・ドイツ文学科修士課程修了。京都産業大学名誉教授。 主要著書:『ドイツ・オカルト事典』同学社。 主要訳書:H. H. エーヴェルス『蜘蛛・ミイラの花嫁』創土社(共訳)、G. マイリンク『緑の顔』創土社、H. H. エーヴェルス『魔法使いの弟子」創土社、G. マイリンク『西の窓の天使』上、下 国書刊行会(共訳)、H. v. クライスト『クライスト全集』第一巻〜第四巻(別巻)沖積舎、など。 |
|
発刊日 |
||
2018年12月5日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-695-7
|
||
 |
三つの国の物語 トーマス・マンと日本人 山口知三 1920年代から1930年代にかけてのトーマス・マンの受容の様態を、ドイツ、アメリカのそれと比べながら、トーマス・マンの実像との日本における落差を、真正面から、深く、徹底的に論じる。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3025円(税込) |
山口知三(やまぐち・ともぞう) 1936年鹿児島県に生まれ。京都大学文学部教授を経て、現在、同大学名誉教授。 著書:『ナチス通りの出版社─ドイツの出版人と作家たち』(共著、人文書院 1989)、『ドイツを追われた人びと─反ナチス亡命者の系譜』(人文書院 1991)、『廃墟をさまよう人びと─戦後ドイツの知的原風景』(人文書院 1996)、 『アメリカいう名のファンタジー─近代ドイツ文学とアメリカ』(鳥影社 2006)など。 訳書:トーマス・マン『非政治的人間の考察』(共訳、筑摩書房 1968-71)、カーチャ・マン『夫トーマス・マンの思い出』(筑摩書房 1975)その他。 |
|
発刊日 |
||
2018年10月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-701-5
|
||
 |
『新文体作法』序説 ─ゴーゴリ『肖像画』を例に─ 齋藤紘一 日本語で自らの考えを相手に明確に伝えるためにはどうすればいいのか、 A I 時代の今、そのことに悩む人は少なくない。本書は概念「ある」 をもとに日本語の成り立ちを解明する驚くべき文法書。ロシア文学翻訳家でもある筆者の手により、今、ゴーゴリを新文体で読むことが可能に! |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
齋藤紘一(さいとう・こういち) 1943年、群馬県生まれ。 東京大学理学部化学科卒。 通産省入省後、課長・審議官を務める。 1993年退官後、ISO(国際標準化機構)日本代表委員、 独立行政法人理事長等をへて現在、翻訳家。 訳 書: フョードル・ソログープ『小悪魔』(文芸社、2005年)、ボリス・ワジモヴィチ・ソコロフ『スターリンと芸術家たち』(鳥影社、2007年)、ワシーリー・グロスマン『人生と運命』(全3巻、みすず書房、2012年)日本翻訳文化賞受賞、『万物は流転する』(みすず書房、2013年)、『システィーナの聖母』(後期作品集、みすず書房、2015年) |
|
発刊日 |
||
2018年10月8日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-705-3
|
||
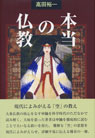 |
本当の仏教
高田裕一
「空」の教えとは? |
|
価格 |
著者略歴 | |
1760円(税込) |
高田裕一(たかだ・ゆういち) 大阪府に生まれる。 1969年、東北大学理学部化学科卒業。 日本化学会、American Chemical Society会員。 書家: 古久保泰石、小説家: 井上光晴に師事。 音響メーカー技術部長としてCDプレーヤーUSA特許取得(US005373495A)し、USA最高級オーディオ協会優秀技術賞にノミネートされる。 現在、東京都に在住し、研究・執筆活動に専念。 「脳波の評価方法及び評価装置」特許出願審査請求中(特願2018-78287)。 著書『しあわせ日記』(論創社)『本当の酒』(長崎出版)『六本木GENJI陽香留』(論創社)『末期ガンからの生還』(ラピュータ)などがある。 |
|
発刊日 |
||
2018年9月13日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-703-9
|
||
 |
根本思想を骨抜きにした『ツァラトゥストラ』翻訳史 並びに、それに関わる日本近代文学
小山修一
ニーチェの命の翻訳はー日本近代文学の死角 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2200円(税込) |
小山修一(こやま・しゅういち、本名・今井修一) 1948年 福岡県生まれ。 中央大学大学院文学研究科独文専攻博士後期課程修了。 1989年4月から2012年3月まで石巻専修大学経営学部准教授。 元『文芸東北』同人 著書:詩集『黄金のひみつ』(鳥影社 2001)、詩集『韓国の星、李秀賢君に捧ぐ』(文芸東北新社 2008)、『「ツァラトゥストラ」入門』(郁文堂 2005)、『ニーチェ「ツァラトゥストラ」を少し深読みするための十五章』(鳥影社 2013)、 『根本思想を骨抜きにした「ツァラトゥストラ」翻訳史─並びに、それに関わる日本近代文学』(鳥影社 2018) 訳書:『ツァラトゥストラ』上(鳥影社 2002)、『ツァラトゥストラ』下( 鳥影社 2003)、『黄金の星はこう語った』上(鳥影社 2011)、『黄金の星はこう語った』下(鳥影社 2011)、『2018改訂 黄金の星はこう語った」(鳥影社 2018)※訳書の原典は、いずれもAlso Sprach Zarathustra |
|
発刊日 |
||
2018年8月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-698-8
|
||
 |
表現主義戯曲/旧東ドイツ国家公安局対作家/ヘルマン・カントの作品/ルポルタージュ論
酒井 府 本書は「表現主義の戯曲」「シュタージと作家達」「ヘルマン・カント」「ルポルタージュ論」などをテーマに、作家達の多様な営為を広い視野のもとに論じる大作。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
本体3,400円+税 |
酒井 府(さかい・おさむ) 1934年東京生まれ。 早稲田大学独文専修修士課程、東京都立大学独文専修博士課程修了。 獨協大学外国語学部名誉教授。 専攻 近現代ドイツ文学。 著書:『ドイツ表現主義と日本─大正期の動向を中心に』早稲田大学出版部、2003年。 訳書:『アンネ・フランク、最後の七カ月』ウィリー・リントヴェル著、共訳・酒井明子、徳間書店、1991年、他。 |
|
発刊日 |
||
2018年7月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-673-5
|
||
 |
草木名の語源
江副水城
草名200種、木名150種収録 |
|
価格 |
著者略歴 | |
4180円(税込) |
江副水城(えぞえ みずき) 1938年熊本県八代市生まれ。 東京大学法学部卒、上場企業(旭化成)に勤務後退職。 趣味は麻雀愛好、動植物観察、言語研究。 著 書:『魚名源』(2009年5月) 『鳥名源』(2010年6月) 『獣名源』(2012年10月) 『蟲名源』(2014年2月) (以上、発行所 株式会社パレード、発売所 株式会社星雲社) |
|
発刊日 |
||
2018年7月2日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-655-1
|
||
 |
新訳 金瓶梅 上巻
田中智行 訳
『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』と並び称される四大奇書 |
|
価格 |
訳者略歴 | |
3850円(税込) |
田中 智行(たなか ともゆき) 1977年、横浜生まれ。 2000年、慶應義塾大学文学部卒業。 2011年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。 日本学術振興会特別研究員(PD)、徳島大学准教授を経て、 現在、大阪大学大学院言語文化研究科准教授。 専門は中国古典文学(白話小説)。 主な論文に、 「『金瓶梅』第三十九回の構成」(『東方学』第119輯、2010) 「『金瓶梅』張竹坡批評の態度」(『東方学』第125輯、2013) などがある。 |
|
発刊日 |
||
2018年5月16日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-675-9
|
||
 |
インゲボルク・バッハマンの文学
髙井絹子
〈作家と作品の全体像に迫る画期的評論〉 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2750円(税込) |
髙井 絹子(たかい きぬこ) 1963年宮崎県生まれ。 大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程(ドイツ語ドイツ文学専攻)単位取得退学。 2012年9月、大阪市立大学大学院で博士(文学)の学位を取得。 現在、大阪市立大学准教授。専攻はドイツ文学。 共訳書 マティアス・ポリティキ『アサヒ・ブルース』松本工房 論文 「インゲボルク・バッハマンの放送劇『マンハッタンの善良な神』─二つの顔をもつ神」『世界文学』第116号 「インゲボルク・バッハマンとウィーン─観念的な地図の書き換えをめぐって」『人文研究』第65巻 「Ingeborg Bachmanns Unter den Mördern und Irren - zur Variierung der Täter-Opfer- Konstellation」『オーストリア文学』第33号 など。 |
|
発刊日 |
||
2018年4月18日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-672-8
|
||
 |
食通のおもてなし観光学
山上 徹
おもてなし観光のウンチクを語るネタ本 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
山上 徹(やまじょう とおる) 出 身 石川県羽咋市 学 歴 日本大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学 商学博士 職 歴 日本大学教授、同志社女子大学教授を経て、 現 職 梅花女子大学食文化学部教授 商学博士 同志社女子大学名誉教授、石川県人会副会長等 主な著書 『食ビジネスのおもてなし学』学文社、2015年 『ホスピタリティ・ビジネスの人材育成』(編著)白桃書房、2012年 『食文化とおもてなし』学文社、2012年 『観光立国へのアプローチ』(共編著)成山堂書店、2010年 『観光の京都論 第二版』学文社、2010年 『ホスピタリティ精神の深化』法律文化社、2008年 『京都観光学 改訂版』法律文化社、2007年 『現代観光・にぎわい文化論』白桃書房、2005年 『観光マーケティング論』白桃書房、2005年 『国際観光論』白桃書房、2004年 他多数 |
|
発刊日 |
||
2018年3月26日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-665-0
|
||
 |
認知コントロールからみた心理学概論
嶋田博行
初学者から〈認知心理学〉の研究者まで |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
嶋田 博行(しまだ ひろゆき) 神戸大学大学院教授 大阪大学人間科学部卒、大学院人間科学研究科博士後期課程単位修得後退学 博士(人間科学) 大阪大学助手、神戸商船大学助教授、教授を歴任 2018年4月より神戸大学名誉教授 |
|
発刊日 |
||
2018年3月22日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-669-8
|
||
 |
ロマン・ロラン著 三つの「英雄の生涯」を読む —ベートーヴェン、ミケランジェロ、トルストイ— 三木原浩史
小説、戯曲、伝記、音楽研究・音楽評論、美術研究、哲学研究、社会批評など……自らが知の英雄だったロマン・ロラン。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
三木原 浩史(みきはら ひろし) 1947年 神戸市生まれ。 1971年 京都大学文学部フランス語学フランス文学科卒業。 1977年 京都大学大学院文学研究科博士課程(フランス語学フランス文学専攻)中退。 経歴 大阪教育大学教育学部助教授、神戸大学大学院国際文化学研究科教授を経て、 現在は、神戸大学名誉教授。シャンソン研究会顧問。 浜松シャンソンコンクール(フランス大使館後援)審査委員長。 専 門 フランス文学・フランス文化論(特に、シャンソン・フランセーズ研究)。 著 書『シャンソンの四季』(彩流社、1994年、2005年改訂増補版)、『シャンソンはそよ風のように』(彩流社、1996年)、『フランス学を学ぶ人のために』(共著、世界思想社、1998年)、『パリ旅物語』(彩流社、2002年)、『シャンソンのエチュード』(彩流社、2005年、2016年改訂版)、『シャンソンのメロドラマ』(彩流社、2008年)、『シャンソンの風景』(彩流社、2012年)、『随想・オペラ文化論』(彩流社、2017年)、『すみれの花咲く頃、矢車菊の花咲く時』(鳥影社、2017年)、『追憶 風薫る季節へ』(彩流社、2017年) 論 考 ロマン・ロラン、シャンソン・フランセーズ、オペラ等に関するもの。 訳 書 みすず書房『ロマン・ロラン全集』、第13巻所収「ニオベ」、第19巻所収「演劇について」(共訳)、ロマン・ロラン『ピエールとリュス』(鳥影社、2016年) |
|
発刊日 |
||
2018年3月20日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-652-0
|
||
 |
世紀末ウィーンの知の光景 西村雅樹 奥深く、多様性をはらむ世紀末ウィーンの文化を、これまで知られている事柄はもとより、ほとんど知られていない知見を豊富に盛り込んで扱う。文学を初め、美術、音楽、建築・都市計画、そしてユダヤ系知識人の動向まで射程に収める。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
西村雅樹(にしむら・まさき) 1947年京都市生まれ。1972年京都大学大学院文学研究科修士課程修了。1979年秋から2年間、オーストリア政府奨学留学生としてウィーン大学留学。愛媛大学教養部講師、広島大学総合科学部講師、助教授、教授、京都大学大学院文学研究科教授を経て、現在、広島大学名誉教授、京都大学名誉教授。ドイツ文学・オーストリア文化研究専攻。 著書:『言語への懐疑を超えて—近・現代オーストリアの文学と思想』(東洋出版、1995年) 『世紀末ウィーン文化探究—「異」への関わり』(晃洋書房、2009年) 訳書:アルブレヒト・ゲース『泉のほとりのハガル』(日本基督教団出版局、1986年) ユーリウス・H・シェプス編『ユダヤ小百科』(共訳、水声社、2012年) |
|
発刊日 |
||
2017年10月31日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-644-5
|
||
 |
甲州・樫山村の歴史と民俗Ⅱ —年中行事・お筒粥・お神楽・山王権現・訂正と再考— 大柴弘子 「樫山」は地図上から消え、限界集落と云われ消滅の危機にある。風化する「樫山」の歴史・民俗をまずは、記録に留めておこうというのが本著の主な目的である。郷土の歴史・文化を忘失することは、自身を見失うことに繋がる。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
大柴弘子(おおしば ひろこ) 昭和16年(1941)生まれ。 昭和19年から33年まで清里村に在住。 昭和22年(1947)4月 清里村立清里小学校入学、昭和28年同小学校卒業。 昭和28年(1953)4月 清里村立清里中学校入学、昭和31年同中学校卒業。 昭和37年(1962)年日本国有鉄道中央鉄道病院看護婦養成所、昭和41年埼玉県立女子公衆衛生専門学院、昭和52年年武蔵大学人文学部社会学科、各卒。平成6‐14年東京都立大学大学院修士課程卒、同大学院博士課程単位取得退学(社会人類学専攻)。 平成29年(2017)4月現在 長野県諏訪市在住。(湖南治療文化研究所主幹) 著書『甲州・樫山村の歴史と民俗―調査資料・解説・覚書』、『18世紀以降近江農村における死亡動向および暮らし・病気・対処法―過去帳分析、村落社会調査による』(以上、鳥影社) 他 |
|
発刊日 |
||
2017年6月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-608-7
|
||
 |
スイス文学・芸術論集 小さな国の多様な世界 スイス文学会編 スイスをスイスたらしめているものは何なのか。文学、芸術、言語、歴史などの総合的な視座から、小さな国の大きく豊かな存在の秘密を明らかにする。 |
|
価格 |
執筆者一覧 | |
2090円(税込) |
大串紀代子(おおぐし・きよこ)獨協大学名誉教授 曽田長人(そだ・たけひと)東洋大学教授 中川裕之(なかがわ・ひろゆき)大阪大学教授 川島隆(かわしま・たかし)京都大学准教授 鍵谷優介(かぎや・ゆうすけ)東洋大学他非常勤講師 若林恵(わかばやし・めぐみ)東京学芸大学教授 新本史斉(にいもと・ふみなり)津田塾大学教授 関口裕昭(せきぐち・ひろあき)明治大学教授 松鵜功記(まつう・こうき)武蔵大学他非常勤講師 橋本由紀子(はしもと・ゆきこ)東京理科大学他非常勤講師 須永恆雄(すなが・つねお)明治大学教授 |
|
発刊日 |
||
2017年6月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-612-4
|
||
 |
夏目漱石 『猫』から『明暗』まで 平岡敏夫 漱石文学は時代とのたたかいの所産であるゆえに、作品には微かな〈哀傷〉が漂う。『猫』から『明暗』までを味読した本書の魅力もそこに関わっている。新たな漱石を描き出す充実した論集。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
平岡敏夫(ひらおか・としお) 1930年香川県生まれ。日本近代文学専攻・文学博士。 筑波大学教授、群馬県立女子大学学長を経て、現在、両大学名誉教授。 日本学術会議会員、中国・韓国・台湾・タイ・アメリカで客員教授等を歴任。 主著に、『日本近代文学の出発』『日露戦後文学の研究』『〈夕暮れ〉の文学史』等の文学史論、『北村透谷研究』『漱石序説』『漱石研究』『「坊つちやん」の世界』『漱石 ある佐幕派子女の物語』『石川啄木の手紙』(啄木賞)『芥川龍之介と現代』『もうひとりの芥川龍之介』『短篇作家 国木田独歩』『森鷗外 不遇への共感』等の作家論、『塩飽の船影』『「舞姫」への遠い旅』『ある文学史家の戦中と戦後』等のエッセイ集、『海辺のうた』『明治』『夕暮』『蒼空』『月の海』『平岡敏夫詩集』『塩飽から遠く離れて』等の詩集がある。 近著は、『文学史家の夢』『佐幕派の文学史』『佐幕派の文学』『「明治文学史」研究明治篇』。 | |
発刊日 |
||
2017年4月11日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-611-7
|
||
 |
断片化する螺旋 ホーフマンスタールの文学における中心と「中心点」 小野間亮子 内在するダイナミズム |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
小野間 亮子(おのま りょうこ) 2012年 東京大学大学院人文社会系研究科を単位取得退学 2013年 博士号取得(文学博士) 現在、東京藝術大学非常勤講師 主な論文:『二様の「新しい小説」—『袖の下のきかぬ男』から読み解くホーフマンスタールのロマーン論』(『オーストリア文学』第31号) | |
発刊日 |
||
2017年2月25日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-604-9 |
||
 |
五感で読むドイツ文学
松村朋彦 五感を媒介に創作の深部に迫る |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
松村朋彦(まつむら・ともひこ) 1959年京都市生まれ。 京都大学大学院文学研究科修士課程(ドイツ語学ドイツ文学専攻)修了。 京都大学大学院文学研究科教授。京都大学博士(文学)。 専門は、近代ドイツ文学・文化史。 著書『越境と内省──近代ドイツ文学の異文化像』(鳥影社、2009年)、『啓蒙と反動』(共著、春風社、2013年)、『映画でめぐるドイツ──ゲーテから21世紀まで』(共著、松籟社、2015年) |
|
発刊日 |
||
2017年3月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-593-6
|
||
 |
デーブリーンの黙示録 —『November 1918』における破滅の諸相— 粂田 文 挫折したドイツ革命を冴えわたる独特の筆致で描いたデーブリーンの大作に挑む研究評論! |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
粂田 文(くめだ・あや) 上智大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻、博士後期課程単位取得退学。文学博士。現在、慶應義塾大学理工学部専任講師。専門はドイツ現代文学。 |
|
発刊日 |
||
2017年2月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-590-5 |
||
 |
ドストエフスキーの作家像
木下豊房 「ドストエフスキーの商品化」マスメディア・出版界の劣化現象を厳しく批判! |
|
価格 |
著者略歴 | |
4180円(税込) |
木下 豊房(きのした とよふさ) 1936年、長崎市生まれ。早稲田大学第一文学部卒、同大学院文学研究科博士課程(「露文学」)単位取得・満期退学。 千葉大学名誉教授 1995年より国際ドストエフスキー協会(IDS)副会長 ドストエーフスキイの会代表(1969年の会発足以来、活動を主導し現在にいたる) 著書: 『近代日本文学とドストエフスキー —夢と自意識のドラマ』成文社(1993) 『ドストエフスキーその対話的世界』成文社(2002) ロシア語論文集: 《Антропология и поэтика творчества Ф.М.Достоевского》(Санкт-Петербург, 2005) (『ドストエフスキーの創作の人間学と詩学』サンクト・ペテルブルグ、2005) 編著: 安藤厚共編『論集・ドストエフスキーと現代』多賀出版(2001) 千葉大学国際研究集会報告論集(ロシア語) 《21 век глазами Достоевского переспективы человечества》(Москва, 2002) (『ドストエフスキーの眼で見た21世紀—人類の将来』(モスクワ、2002) 翻訳: アンナ・ドストエーフスカヤ『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』河出書房新社(1979) Я.Э.ゴロソフケル『ドストエフスキーとカント —「カラマーゾフの兄弟」を読む』みすず書房(1988) トルストイ『人生論』(「人生の名著」12所収)大和書房(1968) |
|
発刊日 |
||
2016年8月19日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-562-2 |
||
 |
現代人権教育の思想と源流 —横田三郎コレクション 横田三郎 今日の教育問題に真摯に取り組もうとする人は、先ずこの本から始め、そしてこの本を乗り越えることが求められる。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
横田三郎(よこた・さぶろう) 1923年 大阪市に生まれる 1944年 滋賀の海軍航空隊に入隊 1945年 終戦で復員後、広島高等師範学校卒業 1947年 京都大学哲学科(教育学専攻)入学 1951年 大阪市立大学(文学部教育学)に勤める。まもなくロシア語の独習とドブロリューボフの翻訳を始める 1983年 大阪市立大学退職(名誉教授)、広島修道大学に勤める 1985年 解放教育研究所所長に就任 2009年 ドブロリューボフ著作選集全18巻の翻訳を完結 2010年 脳内出血のため、高槻市内の病院で死去(87歳) 著書:1967年『現代民主主義教育論』盛田書店 1976年『教育反動との闘いと解放教育』明治図書 論文:1982年「『オブローモフ主義とは何か』の現代的意義」(『社会評論』第37号) 1983年「『神聖喜劇』の中の人権闘争」(大阪市立大学同和問題研究室紀要『同和問題研究』第6号) 1990年「ドブロリューボフの生涯とその思想」(広島修道大学研究叢書第53号) 2007年「ドブロリューボフの今日的意義」(大阪唯物論研究会季報『唯物論研究』第100号) 訳書:1970年『革命的民主主義の教育』(福村出版) 同年 『観念論と体罰への批判』(福村出版) 1972年『反動教育思想批判』(福村出版) 2009年『ドブロリューボフ著作選集』全18巻完結(鳥影社) |
|
発刊日 |
||
2016年8月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-564-6
|
||
 |
ペーター・フーヘルの世界 —その人生と作品 斉藤寿雄 浮かび上がる全体像 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
斉藤寿雄(さいとう ひさお) 1954年長野県生まれ。東京都立大学大学院修了。現在、早稲田大学政治経済学部教授。専門は20世紀のドイツ詩。 主な業績:「ゴットフリート・ベンの抒情性」(『プリスマ』所収、小沢書店)、「ペーター・フーヘル訳詩ノート3」(早稲田大学政治経済学部『教養諸学研究』)、「ペーター・フーヘル訳詩ノート4」(早稲田大学政治経済学部『教養諸学研究』) 翻訳書:『冷戦の闇を生きたナチス』(現代書館、2002年)、『ナチスからの「回心」—ある大学学長の欺瞞の人生』(現代書館、2004年)、『ナチス第三帝国を知るための101の質問』(現代書館、2007年)、『反ユダヤ主義とは何か』(現代書館、2013年)、『第三帝国の歴史』(現代書館、2014年)ほか。 2000年から2002年までレーゲンスブルク大学客員研究員、2010年から2011年まで同大学客員研究員。 |
|
発刊日 |
||
2016年8月9日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-570-7
|
||
 |
カフカと「お見通し発言」 —「越境」する発話の機能— 西嶋義憲 カフカ作品の言語学的分析 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
西嶋義憲(にしじま・よしのり) 1957年埼玉県浦和市(現・さいたま市)生まれ。 1988年広島大学大学院文学研究科博士課程後期中退。 現在 金沢大学人間社会学域経済学類教授。 専門は社会言語学、テクスト言語学。 著書:『カフカと通常性—作品内会話における日常的言語相互行為の「歪み」—』(金沢大学経済学部研究叢書15、2005)。 『カフカ中期作品論集』(共編著、同学社、2011)。 |
|
発刊日 |
||
2016年6月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-551-6
|
||
 |
ディドロ 自然と藝術 冨田和男 フランス革命前夜の知の巨人ディドロ。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
4180円(税込) |
冨田和男(とみた かずお) 1945年 生まれ。 1974年 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程修了。 1978年 同博士課程満期退学、同年4月早稲田大学高等学院教論就任。 2013年 3月退職。 日本十八世紀学会、美学会会員。 著書:『フランス哲学史論集』 (創文社 1985年 共著) 『仏蘭西の智慧と藝術』 (行人社 2002年 共著) ロナルド・グレムズリ編解説『モーペルテュイ、テュルゴ、メーヌ・ド・ビラン 言語表現の起源をめぐって』 (北樹出版 2002年 共訳) |
|
発刊日 |
||
2016年4月21日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-555-4
|
||
 |
ファウスト研究序説 田中岩男 ゲーテと『ファウスト』の魅力を掘り下げる |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
田中岩男(たなか いわお) 1950年北海道生まれ。 1975年東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程(ドイツ文学専攻)修了。 同年、母校の弘前大学人文学部に採用され、助手、講師、助教授を経て現在、弘前大学人文学部教授(思想文芸講座)。 著書・論文:『ゲーテと小説—「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」をよむ』(郁文堂、1999年) 『エルンテ—<北>のゲルマニスティク』(編著、郁文堂、1999年) 『カルポス』(同学社、1995年)に、それぞれ共著者としてゲーテ論。 論文「<病める王子>の快癒—『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』試論」(『ゲーテ年鑑』第31巻、1989年)により日本ゲーテ賞受賞。 |
|
発刊日 |
||
2016年3月25日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-550-9
|
||
 |
釈尊の悟り ─自己と世界の真実のすがた 吉野 博 最古の仏教聖典「スッタニパータ」の詩句、悟りを開いたとされる日本・中国の禅師と |
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
吉野 博(よしの ひろし) 1974年九州大学大学院薬学研究科修士課程修了。 同年、エーザイ株式会社に入社。おもに創薬研究に従事し、 創薬研究本部副本部長などを経て、2010年定年退職。 薬学博士。 |
|
発刊日 |
||
2016年1月11日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-542-4 |
||
 |
ヘルダーリンにおける自然概念の変遷
田野武夫 ヘルダーリンの世界を解明するキーワード「自然」概念の変遷過程を辿る。中期から後期の作品、書簡、論文を詳細に検証し、古代ギリシアから、オリエント、インド、アジアまでを射程に入れる。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2475円(税込) |
田野武夫(たの・たけお) 1970年宮崎市に生まれる。 2003年九州大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。 2004年博士(文学)。現在、拓殖大学政経学部准教授。 |
|
発刊日 |
||
2015年3月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-496-0
|
||
 |
18世紀以降近江農村における死亡動向および暮らし・病気・対処法 —過去帳分析、村落社会調査による— 大柴弘子 調査資料・論文集(調査地:滋賀県野洲市三上・妙光寺・北桜・南桜) |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
大柴弘子(おおしば ひろこ) 1941年生まれる。 1962年日本国有鉄道中央鉄道病院看護婦養成所、1966年埼玉県立女子公衆衛生専門学院、1977年武蔵大学人文学部社会学科、各卒。1994‐2002年東京都立大学大学院修士課程卒、同大学院博士課程単位取得退学(社会人類学専攻)。 職歴:大宮鉄道病院、佐久総合病院健康管理部および日本農村医学研究所、南相木村、信州大学医療技術短期大学部(看護学)、神奈川県社会保険協会健康相談室、昭和大学保健医療学部兼任講師(医療人類学)、各勤務。社会保険横浜中央看護専門学校、東京女子医科大学看護短期大学、厚生省看護研修研究センター等非常勤講師。現在、湘南治療文化研究所主幹(保健師、医学博士)。 |
|
発刊日 |
||
2015年1月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-450-2
|
||
 |
ゲーテ『悲劇 ファウスト』を読みなおす —人間の存在理由を求めて 新妻 篤 ゲーテが約60年をかけて完成した『悲劇 ファウスト』。3つの序曲を含め4つの悲劇、「学者・認識者の悲劇」「グレートヒェン悲劇」「ヘーレナ悲劇」「支配者悲劇」すべてを原文に即して内部から理解しようと研究してきた著者が熱く解き明かす、ファウスト論決定版。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
新妻 篤(にいづま あつし) 1929年札幌生まれ。北海道大学文学部卒(旧制)。ドイツ文学専攻。 北海道大学名誉教授。 論文:「空間の詩人としての芭蕉とリルケ」(独文) 「新渡戸稲造のゲーテ受容」(独文) 「『岩壁』の形象—C.F.マイヤーの詩法」 「ケラーの『緑のハインリヒ』における精神の自由」(独文)、その他 訳書:リルケ『第一詩集』、『白衣の侯爵夫人』(河出書房新社:『リルケ全集』第一巻) アイク『ビスマルク伝』第三巻、第五巻(共訳)、第七巻(ぺりかん社) 『マイヤー名詩選』(大学書林) 『原形ファウスト』(同学社)、その他 |
|
発刊日 |
||
2015年1月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-488-5
|
||
 |
ヘルダーのビルドゥング思想
濱田 真 ヘルダー像の刷新 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3960円(税込) |
濱田 真(はまだ まこと) 1962年生まれ。 慶應義塾大学文学部ドイツ文学科卒業。 ドイツ学術交流会(DAAD)奨学生としてドイツ・ケルン大学留学。 慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程ドイツ文学科単位取得退学。 現在、筑波大学人文社会系教授、日本ヘルダー学会理事、国際ヘルダー学会(IHS)会員。 文学博士(筑波大学)。 専門分野は近代ドイツ文学・思想。 主要著書・論文:『ドイツロマン主義研究』(共著、御茶の水書房、2007年) 「ヘルダーの民謡収集の思想的基盤 年齢説、起源論、パリンゲネジー論」 (日本ヘルダー学会『ヘルダー研究』第17号、2012年)他。 |
|
発刊日 |
||
2014年10月14日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-472-4
|
||
 |
倒錯と芸術 —無のネットワークとフランシス・ベイコン— 嘉陽美彌子 これは誰も読んだことがないほどの独創的な世界構造論であり、その理論を基に、フランシス・ベイコン、パゾリーニなどを論じた芸術論集でもある。物理現象と生命現象、そして存在と無の哲学的命題を、著者は独自の観点から統合する。
|
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
嘉陽美彌子(かよう みやこ) 昭和29年8月13生 沖縄県出身 |
|
発刊日 |
||
2014年6月4日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-446-5 |
||
 |
環境教育論
今井清一/今井良一 環境教育は消費者教育。日本の食品添加物1894種に対し英国は14種。原発輸出も事故を起した場合日本負担になる等知る事が多い。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
今井 清一(いまい せいいち) 1938年 神戸市に生まれる。 神戸大学文学部を経て、1969年 大阪市立大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。 現在、武庫川女子大学名誉教授、元神戸親和女子大学発達教育学部教授、博士(臨床教育学) 。 今井 良一(いまい りょういち) 1972年 神戸市に生まれる。 1992年 京都大学農学部農林経済学科入学。 2004年 同大学院農学研究科生物資源経済学専攻博士後期課程満期退学。 2007年 博士(農学、京都大学)。 現在(2010年〜)神戸親和女子大学発達教育学部・通信教育部非常勤講師(地理学)。 2014年9月より、関西学院大学教職教育研究センター非常勤講師(環境教育論)。 〈専門分野〉日本経済史、歴史学(日本史・東洋史)、環境教育学、地理学(農業地理学) |
|
発刊日 |
||
2014年5月24日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-460-1 |
||
 |
生きられた言葉 ラインホルト・シュナイダーの生涯と作品 下村喜八 シュヴァイツァーと共に20世紀の良心と称えられたラインホルト・シュナイダーは、わが国ではほとんど知られることがなかった。本書はその生涯と思想を初めて本格的に紹介するだけでなく、闇の時代にあって真実を希求し、虚無の中にあって光に向かう意味を問う稀有の書である。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2750円(税込) |
下村喜八(しもむら きはち) 1942年、奈良県に生まれる。 1970年、京都大学大学院文学研究科修士課程修了。 現在 京都外国語大学外国語学部教授。京都府立大学名誉教授。 主な論文: 「『親和力』と『色彩論』」 「ゲーテの『タッソー』における内なる分裂」 「ラインホルト・シュナイダーの『カモンイスの苦悩』」 「破壊された神の像─ラインホルト・シュナイダーの『ヴィーンの冬』」 翻訳: ラインホルト・シュナイダー『カール五世の前に立つラス・カサス』(未来社、1993年) 『ブルンナー著作集 第7・8巻 フラウミュンスター説教集Ⅰ・Ⅱ』(教文館、1996年) |
|
発刊日 |
||
2014年7月2日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-461-8 |
||
 |
R・Z・ベッカーの民衆啓蒙運動 近代的フォルク像の源流 田口武史 ベッカーの著作と彼と同時代の啓蒙論・社会現象からVolkの概念とその社会的・文化的機能の変化を明らかにする。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2640円(税込) |
田口武史(たぐち・たけふみ) 1972年大分県に生まれる。 2004年九州大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。 2011年博士(文学)。松山大学を経て、現在、長崎外国語大学外国語学部准教授。 |
|
発刊日 |
||
2014年3月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-451-9 |
||
 |
境界としてのテクスト カフカ・物語・言説 三谷研爾 物語のテクストから同時代のコンテクストへ |
|
価格 |
著者略歴 | |
1870円(税込) |
三谷研爾(みたに・けんじ) 1961年京都府に生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程中退。博士(文学)。現在、大阪大学大学院文学研究科教授、専門はドイツ・オーストリア文学、中欧文化論。 著書に『ドイツ文化史への招待 芸術と社会のあいだ』(編著、2007年 大阪大学出版会)、『世紀転換期のプラハ モダン都市の空間と文学的表象』(2010年 三元社)などがある。 |
|
発刊日 |
||
2014年3月20日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-440-3
|
||
 |
語りの多声性 デーブリーンの小説『ハムレット』をめぐって 長谷川 純 物語を〈語る〉という行為、物語を〈読む〉という行為、そのどちらにとっても魅力的なテクストがデーブリンである。ここにしかないものは何かを著者は読みといていく。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
長谷川純(はせがわ・じゅん) 1957年東京に生まれる。 1983年上智大学大学院文学研究科(ドイツ文学専攻)博士前期課程修了。 ルール大学、ボン大学に学ぶ。 2012年上智大学大学院文学研究科(ドイツ文学専攻)博士課程修了。 博士(文学)。外資系企業勤務を経て、現在、日系企業グループにて「語りと経験」をテーマに、人材育成に携わる。 |
|
発刊日 |
||
2013年10月5日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-416-8 |
||
 |
飯野布志夫 著作集㈠ 言葉の起こり 飯野布志夫 『古事記』から言葉のルーツへ |
|
価格 |
著者略歴 | |
3520円(税込) |
飯野布志夫(いいの ふしお) 昭和7年12月24日、鹿児島県生まれ。 広島大学教育学部高等学校教育科理科卒。 文語方言研究所主宰。 著書:『神々の性展 飯野布志夫 著作集㈡』 『覇道無惨 ヤマトタケル 飯野布志夫著作集 ㈢』 『眠る邪馬台国 飯野布志夫 著作集㈣』 |
|
発刊日 |
||
2013年10月2日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-421-2 |
||
 |
飯野布志夫 著作集㈡ 神々の性展 飯野布志夫 『古事記 神代巻』の真実 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1760円(税込) |
飯野布志夫(いいの ふしお) 昭和7年12月24日、鹿児島県生まれ。 広島大学教育学部高等学校教育科理科卒。 文語方言研究所主宰。 著書:『言葉の起こり 飯野布志夫 著作集㈠』 『覇道無惨 ヤマトタケル 飯野布志夫著作集 ㈢』 『眠る邪馬台国 飯野布志夫 著作集㈣』 |
|
発刊日 |
||
2013年7月19日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-412-0 |
||
 |
『ドイツ伝説集』のコスモロジー —配列・エレメント・モティーフ— 植 朗子 『グリム童話集』、『ドイツ神話(学)』と並ぶドイツ民俗学の基底であり、民間伝承蒐集のさきがけとなった、グリム兄弟『ドイツ伝説集』の内面的実像を明らかにする試み。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
植 朗子(うえ あきこ) 1977年、和歌山県新宮市生まれ。 大阪市立大学文学部国語・国文学科卒。大阪市立大学大学院文学研究科修士課程修了(ドイツ文学)。神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程後期修了、博士号(学術)取得。 神戸大学 ドイツ語講師 神戸松蔭女子学院大学 非常勤講師 大和大学(新設) 非常勤講師 大手前大学 学習支援センターチューター 神戸大学大学院 国際文化学研究科 異文化研究交流センター(IRec) 協力研究員 |
|
発刊日 |
||
2013年6月27日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-414-4 |
||
 |
激動のなかを書きぬく ──20世紀前半のドイツの作家たち 山口知三 自殺したクラウス・マン、沈黙のなかで忘れ去られたヴォルフガング・ケッペン、それにトーマス・マン。あの時代を書きぬき・生きぬいた三人の姿を描く。トマース・マン論「転身の構図」も収録。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
本体2,900円+税 |
山口知三(やまぐち・ともぞう) 1936年、鹿児島県に生まれる。 京都大学文学部教授を経て、現在、同大学名誉教授。 著書『ナチス通りの出版社──ドイツの出版人と作家たち1886-1950』(共著、人文書院 1989) 『ドイツを追われた人びと──反ナチス亡命者の系譜』(人文書院 1991) 『廃墟をさまよう人びと──戦後ドイツの知的原風景』(人文書院 1996) 『アメリカいう名のファンタジー──近代ドイツ文学とアメリカ』(鳥影社 2006)など。 訳書 トーマス・マン『非政治的人間の考察』(共訳、筑摩書房 1968-71) カーチャ・マン『夫トーマス・マンの思い出』(筑摩書房 1975)その他。 |
|
発刊日 |
||
2013年4月25日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-398-7 |
||
 |
放浪のユダヤ人作家 ヨーゼフ・ロート
平田達治 1939年パリに死す |
|
価格 |
著者略歴 | |
3520円(税込) |
平田達治(ひらた・たつじ) 1934年奈良県生まれ。大阪大学名誉教授。 著書 『ウィーンのカフェ』(大修館書店) 、『輪舞の都ウィーン』(人文書院) 、『中欧・墓標をめぐる旅』(集英社新書)ほか。 訳書 『ヨーゼフ・ロート小説集・全4巻』(共訳、鳥影社) 、ロート『放浪のユダヤ人とエッセイ二篇』(鳥影社)、ロート『ラデツキー行進曲』(鳥影社) 、ロート『果てしない逃走』(岩波文庫) 、H・ハウマン『東方ユダヤ人の歴史』(共訳、鳥影社) 、J・シュレーア『大都会の夜』(共訳、鳥影社) 、K・クライマイヤー『ウーファ物語』(共訳、鳥影社)ほか。 |
|
発刊日 |
||
2013年3月20日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-393-2 |
||
 |
クライスト、認識の擬似性に抗して ──その執筆手法── 眞鍋正紀 現実認識とそれを表現するときに生じる乖離や差異がクライストには問題であった。では彼はどのように解決しようとしたのか? それは彼の主要な作品『チリの地震』『聖ツェツィーリエ』『ロカルノの女乞食』『ペンテジレーア』のなかに具体的に探る。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2200円(税込) |
眞鍋正紀(まなべ・まさのり) 1971年愛媛県生まれ。 上智大学大学院研究科ドイツ文学専攻博士後期課程単位修得後退学(2004年)。同大学院博士後期課程修了、論文博士(文学)(2011年)。 主要業績:学術論文「小説の脚色に賭けられるもの──クライスト/ロメール/ジーバーベルクにおけるテクストとイメージの関係──」(渋谷哲也編著『映画におけるイメージとテクストの関係について──ドイツとフランスのニューシネマを例に──』日本独文学会発行62号、2009年10月、21-46頁。) 翻訳「ウヴェ・ペルクゼン『図像の世界市場(抄)』」(『環』、藤原書店、2009年夏38号、170-183頁。) |
|
発刊日 |
||
2012年2月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-336-9 |
||
 |
詩人ヘルヴェークとハイネ
可知正孝 「二月革命」「三月革命」とつづく激動の時代に交差した二人の詩人──その出会いと齟齬・批判をダイナミックに論じる初めての具体的試み。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1870円(税込) |
可知正孝(かち・まさたか) 1937年岐阜県生まれ 東京都立大学大学院博士課程修了。 職歴 法政大学第二高等学校教諭 岐阜大・名工大・愛知学院・中京女子大・日福大・名城大・ 信州大・名市大・南山大非常勤講師 現在、愛知県立大学名誉教授 著書 『テューリンゲンの森』(鳥影社)、『日独の民俗・諺にみる動物比較 序論』(鳥影社)、『詩人ハイネ』(鳥影社) 共著・論文等 『世界の文学Ⅰ』(汐文社)、『ハイネとその時代 井上正蔵記念論文集』(朝日出版社)、勝間淳視遺稿集『ハイネとその文学』(同学社)、『マルクスカテゴリー辞典』(青木書店)、『ハイネ研究』第5・6・7・8巻(東洋館出版社) |
|
発刊日 |
||
2012年1月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-334-5 |
||
 |
別の言葉で言えば ホフマン、フォンターネ、カフカ、ムージルを翻訳の星座から読みなおす ペーター・ウッツ 著 新たな意義を展開する翻訳論の登場 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2970円(税込) |
ペーター・ウッツ(Peter Urz) 1954年生まれ。ローザンヌ大学文学部教授。 専門はドイツ近現代文学。翻訳論。 著書に『テクストの中の眼と耳──ゲーテ時代の文学的感覚受容』、『ほとりでの踊り──ローベルド・ヴェルザーの〈現在時文体〉』(いずれも未邦訳)他。 新本・史斉(にいもと・ふみなり) 1964年広島生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。 現在、津田塾大学国際関係学科教授。 専門はドイツ語文学、翻訳論。 論文:「〈はじめて書きつけた慣れない手つきの文学〉に出会うための散歩──ローベルト・ヴェルザーの『散歩』論」(『ドイツ文学』)他。 訳書:『スイス文学三人集』(共訳、行路社)、『ヨーロッパは書く』(共訳、鳥影社)、『氷河の滴──現代スイス女性作家作品集』(共訳、鳥影社)、『ローベルト・ヴェルザー作品集1』(鳥影社)他。 |
|
発刊日 |
||
2011年7月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-304-8
|
||
 |
詩人ハイネ ─作品論考と他作家との対比─ 可知正孝 長年にわたるハイネ研究の成果を問う論文集。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
可知政孝(かち・まさたか) 1937年岐阜県生まれ。 東京都立大学大学院博士課程修了。 職歴 法政大学第二高等学校教諭、岐阜大・名工大・愛知学院・中京女子大・日福大・名城大・信州大・名市大・南山大非常勤講師 現在、愛知県立大学名誉教授。 著書『チューリンゲンの森』(鳥影社) 、『日独の民俗・諺にみる動物比較 序論』(鳥影社) 共著・論文等『世界の文学Ⅰ』(汐文社)、『ハイネとその時代 井上正蔵記念論文集』(朝日出版社)、勝間淳視遺稿集『ハイネとその文学』(同学社)、『マルクスカテゴリー辞典』(青木書店)、『ハイネ研究』第5・6・7・8巻(東洋館出版社)ほか。 |
|
発刊日 |
||
2011年1月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-270-6 |
||
 |
ゲーテ『親和力』における「倫理的なもの」 ──F・H・ヤコービの「スピノザ主義」批判との関連において 中井真之 「デモーニッシュなもの」「汎神論的自然観」「意識と無意識」等々と関連づけて、ゲーテとスピノザ主義の関連を跡づける。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
中井真之(なかい・さなゆき) 1966年東京生まれ。 上智大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻博士後期課程満期退学。 2008年7月、上智大学大学院で博士(文学)の学位を取得。 現在、上智大学助教。専門は、ドイツ文学。 主要論文:「F・H・ヤコービとゲーテにおけるスピノザの受容──スピノザ論争の時期を中心に──」(『上智大学ドイツ文学論集』44(2007)所収)。 「ゲーテにおける「デモーニッシュなもの」──「神性」の理解との関わりにおいて──」(『ドイツ文学』138(2008)所収)。 |
|
発刊日 |
||
2010年12月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-268-3 |
||
 |
甲州・樫山村の歴史と民俗 ──調査資料・解説・覚書── 大柴弘子 古の奈良・平安時代からの伝承が残る樫山の地名は、2004年北杜市の誕生にともない、地図上から消えた。貴重な歴史を後世に伝えようと、調査を重ねてきた著者の郷土愛が本書を完成させた。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
大柴弘子(おおしば ひろこ) 1942年生まれ。 1962年国鉄中央鉄道病院看護婦養成所、1966年埼玉県立女子公衆衛生専門学院、1977年武蔵大学人文学部社会学科、各卒。1994-2002年東京都立大学大学院修士課程卒・同大学院博士課程単位取得退学(社会人類学専攻)。 信州大学医療技術短期大学助教授(看護学)、昭和大学保健医療学部兼任講師(医療人類学)等を経て、現在、湖南治療文化研究所主幹(保健師、医学博士)。 |
|
発刊日 |
||
2010年12月1日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-272-0 |
||
 |
ゲーテ『ファウスト』(第一部)釈註
渡邉信生 『ファウスト』を深く読むために |
|
価格 |
著者略歴 | |
本体5,600円+税 |
渡邉信生(わたなべ・のぶお) 1926年佐賀県生まれ。 九州大学文学部独語独文学科卒業。同大学院中退(旧制)。 山口大学教養部教授、九産大国際文化学部教授を経て、現在、山口大学名誉教授。専門は、ヘルマン・ヘッセ、ゲーテ。 訳書:「ヘルマン・ヘッセの作品における女性の役割」(共訳)(『ヘルマン・ヘッセをめぐって──その深層心理と人間像』所収、三修社) |
|
発刊日 |
||
2010年6月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-239-3 |
||
 |
越境と内省 近代ドイツ文学の異文化像 松村朋彦 ヨーロッパ、オリエント、アメリカ、南太平洋──異文化にかんするドイツ人の意識と思考を、旅行記、小説、詩、戯曲、オペラなどさまざまなテクストから読み解く。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2750円(税込) |
松村朋彦(まつむら・ともひこ) 1959年京都市生まれ。 京都大学大学院文学研究科修士課程(ドイツ語学ドイツ文学専攻)修了。 京都大学文学部助手、京都府立大学文学部講師・助教授を経て、現在、京都大学大学院文学研究科准教授。京都大学博士(文学)。専門は、近代ドイツ文学・文化史。 著書・訳書『ハンス・カロッサ全集』第7巻(共訳、臨川書店、1966年)、 『フロイデ独和辞典』(共編、白水社、2003年) 主要論文「読書する恋人たち──『神曲』、『ヴェルテル』、『朗読者』」(『ゲーテ年鑑』第44巻、2002年)、「越境する文学──ゲーテにおける〈移住〉のモティーフ」(『ドイツ文学』第110巻、2003年)ほか。 |
|
発刊日 |
||
2009年10月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-206-5 |
||
 |
カール・フィリップ・モーリッツ ──美意識の諸相と展開── 山本惇二 本邦初の本格的モーリッツ研究書 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3960円(税込) |
||
発刊日 |
||
2009年8月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-188-4 |
||
 |
トーマス・マンの青春 全初期短編小説を読む
岡光一浩 細心の注意を払って読み解くことで、若い彼の文学の豊かさとその深層にひそむ真実を、具体的に分かりやすく紹介する。
|
|
価格 |
著者略歴 | |
3960円(税込) |
岡光一浩(おかみつ・かずひろ) 1943年山口県生まれ。 広島大学大学院修士課程(独語独文学専攻)修了。 北海道教育大学、北海道大学勤務を経て、山口大学教授として定年退職。現在、山口大学名誉教授。専門は、世紀転換期のドイツ文学。 著書・論文;「ナルシスの夢」(『中欧──その変奏』所収、鳥影社)、「レオポルト・アンドリアン」(『オーストリア文学10号』所収)、「ウィーン・カフェの歴史」(『コーヒー文化研究1号』所収)他多数。 |
|
発刊日 |
||
2009年2月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-162-4 |
||
 |
芸術に関する幻想
W・H・ヴァッケンローダー 芸術への深い愛と敬虔な心 |
|
価格 |
訳者略歴 | |
1650円(税込) |
毛利真実(もうり・まみ) 1961年兵庫県県生まれ 慶應義塾大学文学部独文学科卒業 神戸大学大学院文化学研究科博士課程修了 学術博士(神戸大学) |
|
発刊日 |
||
2009年2月10日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-165-5 |
||
 |
ドイツ文化を担った女性たち─その活躍の軌跡
ゲルマニスティネンの会 編 広範囲なジャンルが対象 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
光末紀子(みつすえ・のりこ) 1940年生まれ。神戸大学名誉教授。 専門分野 ドイツ近現代詩、ジェンダー論。 奈倉洋子(なぐら・ようこ) 1945年生まれ。京都教育大学名誉教授。 専門分野 ドイツ文学・文化、比較文化 宮本絢子(みやもと・あやこ) 1943年生まれ。日本女子大学人間社会学部教授。 専門分野 ドイツ語圏女性文学 |
|
発刊日 |
||
2008年10月15日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-156-3 |
||
 |
近代日本のドイツ語学者 上村直己 日本の近代化に大きな役割を果たしたドイツ。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
上村直己(かみむら・なおき) 1939年、鹿児島県に生まれる。 九州大学文学部ドイツ文学科卒業。熊本大学名誉教授、日本独学史学会々長、 熊本学園大学非常勤講師。博士(文学)。 専門分野 独逸学史・日独文化交流史、比較文化。 著書『明治期ドイツ語学者の研究』(多賀出版)、『西條八十とその周辺』(近代文芸社)、『九州の日独文化交流人物誌』(熊本大学文学部地域科学科)。 論文「リヒトホーフェンの見た幕末・明初の九州」、「マールブルク留学時代の宇良田唯子」、「ゲルマニスト長江藤次郎の留学」他多数。 |
|
発刊日 |
||
2008年10月7日 |
||
ISBN |
||
978-4-86265-155-6 |
||
 |
否定詩学─カフカの散文における物語創造の意志と原理
尾張充典 カフカの作品世界を一義的な世界像に還元すべきではない。この地平からカフカ特有の創作原理を導き、その詩学を明らかにする。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3850円(税込) |
尾張充典 1967年愛知県生まれ。 東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。ドイツ文学専攻。 九州産業大学准教授。博士(文学)。 著書『カフカ初期作品論集』(同学社、2008年)(共著) |
|
発刊日 |
||
2008年7月15日 |
||
ISBN |
||
978-4862651389 |
||
 |
日独の民俗・諺にみる動物比較 序論 ─ねずみ、狐、カラス、蛇、猿、兎─ 可知正孝 日本とドイツの俗信の対比──その共通性・類似性を示すことによって、それぞれの文化の背後に横たわっているものを際立たせる試み。
|
|
価格 |
著者略歴 | |
1980円(税込) |
可知政孝(かち・まさたか) 1937年岐阜県生まれ。 東京都立大学大学院博士課程修了。 愛知県立大学名誉教授。 著書『チューリンゲンの森』鳥影社 共著『世界の文学Ⅰ』(汐文社)、『マルクスカテゴリー辞典』青木書店、『ハイネ研究』第5・6・7・8巻 東洋館出版社ほか。 |
|
発刊日 |
||
2008年3月30日 |
||
ISBN |
||
978-4862651228 |
||
 |
経験はいかにして表現へともたらされるのか ─M・フリッシュの「順列の美学」─ 葉柳和則 私は私をいかに語りうるのか |
|
価格 |
著者略歴 | |
本体4,400円+税 |
葉柳和則(はやなぎ・かずのり) 1963年徳島県に生まれる。1997年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得後中退。 1997-1999スイス政府給費留学生・チューリッヒ大学第一哲学部。2008年博士(文学)現在長崎大学環境科学部准教授。 専門 現在ドイツ語圏文学・文化・文化社会学。 著書『中欧-その変奏』鳥影社(共著1998)、『環境と人間』九州大学出版会(共著、2004) |
|
発刊日 |
||
2008年3月30日 |
||
ISBN |
||
978-4862651242 |
||
 |
グリムにおける魔女とユダヤ人 ──メルヒェン・伝説・神話 奈倉洋子 グリムのメルヒェン集と伝説集を中心に、『ドイツ神話学』やヘーベルの『暦物語』までを踏まえて、魔女とユダヤ人の描かれ方、その変化の実態と意味を探る。
|
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
奈倉洋子(なぐら・ようこ) 京都教育大学教授。専門分野、ドイツ文学・文化、比較文学・文化。 著書『ドイツ民衆文化 ベンケルザング』(彩流社)、『日本の近代化とグリム童話』(世界思想社) 編訳書『ドイツ語圏の女性作家─文学と映画』(共編訳、早稲田大学出版部)、『女と男の変奏曲(ドイツ語圏女性作家小説集)』(共編訳、早稲田大学出版部)、『女たちのドイツ─東と西の対話』(共編訳、明石書店)他。 |
|
発刊日 |
||
2008年3月20日 |
||
ISBN |
||
978-4862651198 |
||
 |
ドナウのほとりの三色旗 末永豊 歴史と文化の彩り5論文
|
|
価格 |
著者略歴 | |
1650円(税込) |
末永 豊(すえなが・ゆたか) 1942年生まれ。東京教育大学大学院修士課程修了 現在、岐阜大学地域科学部教授。専門分野、ドイツ文学・文化。 訳書に『物語の森へ 物語理論入門』(共訳)法政大学出版局、 著書に『文化と風土の諸相』(共編著)文理閣、論文に「若きマンにおけるイロニーの問題」東海ドイツ文学会編「ドイツ文学研究13」等がある。 |
|
発刊日 |
||
2008年1月25日 |
||
ISBN |
||
978-4862651082 |
||
 |
ギュンター・グラスの世界
依岡隆児 つねに実験的方法に挑み、政治と社会から関心を失わなかったノーベル賞受賞作家グラス。彼の仕事を真正面から論ずる日本で初めての試み。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
依岡隆児(よりおか・りゅうじ) 1961年高知県に生まれる。 東京都立大学大学院人文科学研究科、独文学博士課程中途退学、博士(文学)(東北大学) 現在;徳島大学教授 論文;「ギュンター・グラス『ブリキの太鼓』について」(東京都立大学人文学部『人文学報』第208号)他。 訳書;ギュンター・グラス『女ねずみ』(共訳、国書刊行会)、ギュンター・グラス『鈴蛙の呼び声』(共訳、集英社) |
|
発刊日 |
||
2007年4月15日 |
||
ISBN |
||
978-4862650658
|
||
 |
フリードリヒ・シラー 美学=倫理学用語辞典 序説 ユ-リア・ヴェルンリ 難解なシラーの基本的用語を網羅し、その体系化をはかり、明快な解釈をほどこす。シラーの全思想を概観する上で打ってつけの書。 |
|
価格 |
訳者略歴 | |
2640円(税込) |
馬上徳(まがみ・めぐみ) 1941年東京に生まれる。慶應義塾大学大学院文学研究科、独文学修士課程修了。現在、成蹊大学教授(法学部) 論文:F・シラー「フィエスコの反乱」『成蹊法学』35号(1992年)所収 訳書:F・シラー「哲学的書簡」『成蹊法学』40号(1995年)所収 その他 |
|
発刊日 |
||
2007年1月 |
||
ISBN |
||
978-4862650528 |
||
 |
アメリカいう名のファンタジー 近代ドイツ文学とアメリカ 山口知三 19世紀半ばから20世紀半ばにかけていかなるファンタジーを紡いだのか。 |
|
価格 |
著者略歴 | |
3080円(税込) |
山口知三(やまぐち・ともぞう) 1936年、鹿児島県に生まれる。 京都大学文学部教授を経て、現在、同大学名誉教授。 著書『ナチス通りの出版社──ドイツの出版人と作家たち1886-1950』(共著、人文書院 1989) 『ドイツを追われた人びと──反ナチス亡命者の系譜』(人文書院 1991) 『廃墟をさまよう人びと──戦後ドイツの知的原風景』(人文書院 1996) 訳書 トーマス・マン『非政治的人間の考察』(共訳、筑摩書房 1968-71) カーチャ・マン『夫トーマス・マンの思い出』(筑摩書房 1975) その他 |
|
発刊日 |
||
2006年10月20日 |
||
ISBN |
||
978-4862650252 |
||
 |
日本的エロティシズムの眺望 視覚と触覚の誘惑 元田與市 日本人は裸体に関心がなかった!— |
|
価格 |
著者略歴 | |
2090円(税込) |
元田與市(もとだ・よいち) 1957年、大分県に生まれる。 専攻は江戸時代の文学と文化。現在、兵庫県立大学環境人間学部教授。 著書『雨月物語の探求』(翰林書房、1993) 『秋成綺想 十八世紀知識人の浪漫と現実』(双文社出版、2003) |
|
発刊日 |
||
2006年9月30日 |
||
ISBN |
||
978-4862650177 |
||
 |
シュトルム・回想と空間の詩学
加藤丈雄 シュトルムの文学的営為の全体像 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
加藤丈雄(かとう たけお) 1954年生まれ。京都府立大学文学部助教授。 編著訳書 『シュトルム文学新論集』(共編・共著)、鳥影社、2003年。「それでもなお、希望が──H.ドミーン、R.アウスレンダーの詩について──」、京都府立大学『学術報告 人文・社会』第57号、2005年。「閉ざされた都市と市門のむこう──『チリの地震』の空間論的考察──」、日本独文学会西日本支部『西ドイツ文学』第4号、1992年。「ヒルデ・ドミーン詩抄(一)」、『季刊 現代文学』72号、2005年。「ローゼ・アウスレンダー詩抄(一)~(三)」『季刊 現代文学』68~70号、2003~04年、他。 |
|
発刊日 |
||
2006年3月20日 |
||
ISBN |
||
978-4886299772 |
||
 |
南方熊楠と「事の学」
橋爪博幸 南方熊楠の思想に迫る |
|
価格 |
著者略歴 | |
2420円(税込) |
橋爪博幸(はしづめ・ひろゆき) 1970年群馬県生まれ。2000年、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。2004年、博士号(人間・環境学)取得。 現在、桐生短期大学生活科学科専任講師。論文として「神社合祀と史跡の滅却」(『熊楠研究』第2号、2000年)など。 |
|
発刊日 |
||
2005年11月20日 |
||
ISBN |
||
978-4886299318 |
||
 |
シュトルム文学新論集 協会設立二十周年記念 日本シュトルム協会 編 21世紀のシュトルム |
|
価格 |
著者略歴 | |
2640円(税込) |
||
発刊日 |
||
2003年9月15日 |
||
ISBN |
||
978-4886297730 |
||
 |
シュニッツラーの家庭崩壊劇
岡野安洋 シュニッツラーの現代性 |
|
価格 |
著者略歴 | |
2090円(税込) |
岡野安洋 1948年東京生まれ。 立教大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻博士課程満期退学。 現在、北里大学助教授。 主要著書 『探求 ドイツの文学と言語』(共著)東洋出版 『オーストリア』(共著)早稲田大学出版部 『ネーミング辞典』(共著)学研 他。 |
|
発刊日 |
||
2003年7月30日 |
||
ISBN |
||
978-4-88629-757-0 |
||
HOME>研究書 |
||